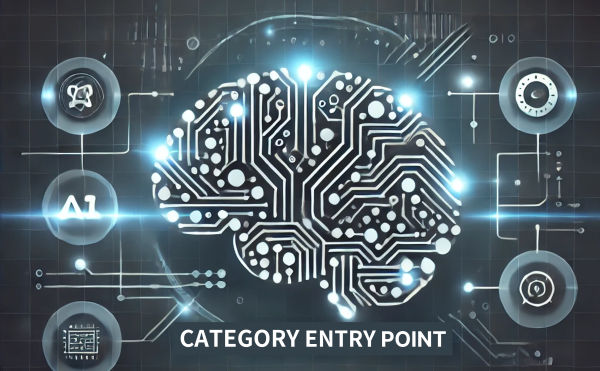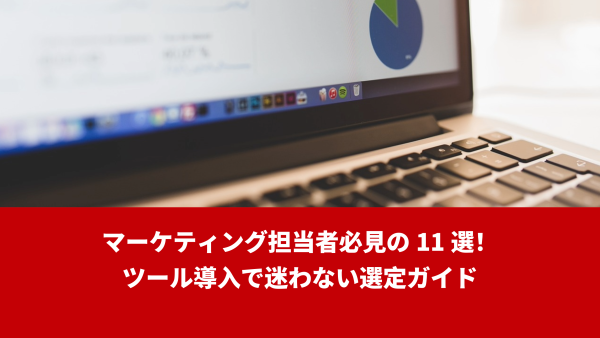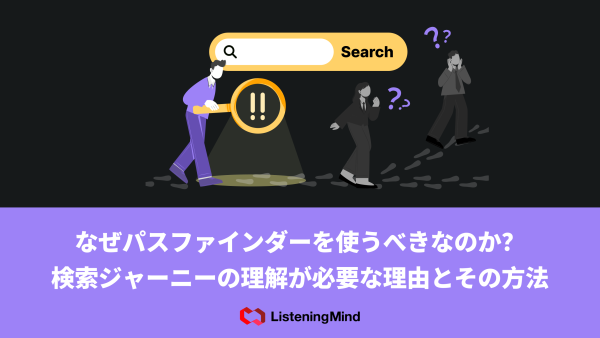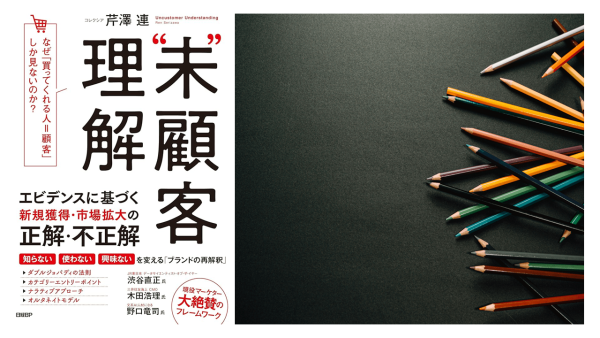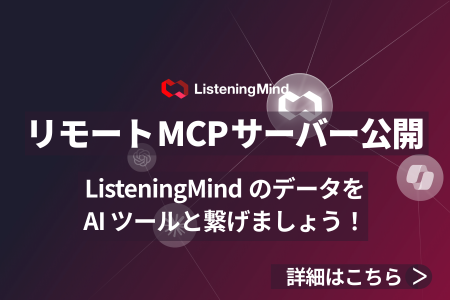?一行まとめ
AI時代のECにおいて重要なのは、SEOを手放すことではなく、GEOと組み合わせて「人・検索エンジン・AI」のすべてに最適化されたコンテンツ戦略を構築することです。
ECを取り巻く検索環境の変化
生成AIの台頭により、従来の“検索からの集客”が通用しづらくなってきています。
これまでオーガニック検索を成長エンジンとしてきた多くのECサイトにとっては、いま、検索起点の流入構造そのものが揺らぎつつある状況です。
AIの普及によってユーザーの検索行動が変化し、従来のように自然検索だけに依存することが、リスクとなりつつあります。
「SEOはもう終わった」「検索エンジン最適化は時代遅れだ」
—そんな言説が飛び交う今、マーケターが向き合うべきは、それが本当に本質を突いているのかどうか、という視点です。結論から言えば、“検索という行為”がなくなるわけではありません。変わるのは、検索によって表出する消費者の意図と、その意図が解決されるプロセスの構造なのです。
つまり、「SEOをやめるべきか?」という問い自体が、そもそも的外れなのです。
マーケターが本当に向き合うべきなのは、既存のSEO戦略をいかに進化させ、GEOとどう結びつけていくかという問いです。
AI時代の検索がもたらす新しいルール
ChatGPT、GoogleのAI Overview、Perplexityなど、生成AIを活用した検索体験は急速に進化しており、従来の検索結果ページ(SERP)の代わりとなる情報提示が当たり前になりつつあります。
ChatGPT、GoogleのAI Overview、Perplexityなどの生成AIによる検索体験は、急速に進化しており、従来の検索結果ページ(SERP)に代わり、AIが直接情報を提示するスタイルが、ユーザーの検索体験として定着しつつあります。
では、AIによって検索結果ページはどのように変化したのでしょうか?
今や、検索結果の上段にはリンクではなく、AIが複数の情報源を統合・要約した「ハイライト」が表示されるようになりました。
ユーザーはこの要約だけで十分な情報を得られるので、従来のようにリンクをクリックする必要がなくなってきているのです。
実際、SparkToroが2024年に発表した調査では、米国の検索のうち58.5%が“ゼロクリック”で完結し、1,000回の検索のうち外部サイトに遷移したのはわずか360回であったことが明らかになっています。
これは、すべてのブランドが直視すべき“新しい検索の常識”と言えます。
SEOからGEOへ─戦略思考のパラダイムシフト
まず整理しておきたいのは、「SEOとは何か?」という前提です。
もし、SEOを「キーワードに合わせたメタタグの設定」「被リンクの獲得」「検索エンジンに好まれる構造の整備」といったテクニカルな対策として捉えているなら、GEOの登場に戸惑いを感じるのも無理はありません。
しかし、すでに「ユーザーが知りたいことは何か?」という“検索意図(インテント)”に注目し、トピックやページ構成を最適化してきたのであれば、GEOはその延長線上にある概念です。
?GEOの目的とは?
では、GEOにおける本質的な目的とは何でしょうか?
それは、「検索エンジンで1位を取ること」ではなく、AIが情報を生成・要約する際に、自社のコンテンツが“参照される存在になること”です。
言い換えれば、AIが最初に思い浮かべ、引用し、信頼する情報源となることこそが、これからの検索最適化における新たなゴールなのです。
AIが評価するコンテンツとは?
では、AIはどのようなWebページを優先的に参照するのでしょうか?
答えはシンプルです。
人にとって価値のある情報を持つページは、AIにとっても信頼に足る情報源であるということです。
近年SEOで重視されてきた、GoogleのE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、今やAIにとっても、重要な評価軸となっています。
?EC領域でのE-E-A-T実装ポイント
| 指標 | コンテンツに必要な要素 |
|---|---|
| Experience(経験) | 実際の使用体験を反映した具体的な説明 |
| Expertise(専門性) | 商品カテゴリに対する深い理解や解説 |
| Authoritativeness(権威性) | 業界認定や外部メディアでの引用実績 |
| Trustworthiness(信頼性) | 明確なポリシー、実ユーザーによる信頼できるレビュー |
特にECコンテンツにおいては、「商品説明をただ並べる」だけでは不十分です。
E-E-A-Tの要素がしっかりと盛り込まれているかどうかが、AIからの評価を左右します。
では、こうした変化はEC企業にとって“ピンチ”なのでしょうか、それとも“チャンス”なのでしょうか?
構造化された商品ページやカテゴリーページを、ユーザーが求める情報や体験を的確に届ける設計に変えていくことで、それらのページはGEO戦略における“資産”として機能するようになります。
GEOにおける成功とは、単に構造を整えることではなく、AIが「この情報は引用に値する」と判断するだけの価値を、ページの中にどう組み込むかにかかっているのです。
実務ガイド①ECサイトにおけるSEO+GEO統合戦略の進め方
AI時代の検索最適化は、「SEOかGEOか」ではなく、両者をいかに統合的に実装するかが鍵になります。
ここでは、ECサイトにおける実践ステップを3段階で整理します。
ステップ1:商品ページを“二重構造”で設計
商品ページは、SEOとGEOそれぞれの要件を同時に満たす「二重構造」で設計する必要があります。
SEO観点(維持):タイトルタグ、メタディスクリプション、ALTテキスト(画像の代替テキスト)、適切なキーワード挿入などの基本的な構造
GEO観点(強化):専門性が伝わる説明、具体的かつ独自性のある製品ページの説明
たとえば、
×「高級素材を使用しています」ではなく、
○「耐久性に優れた600Dポリエステルを採用しており、雨の日でもバッグの内部が濡れにくい構造です」
といったように、“高級素材”という抽象的な表現を、具体的な素材名と機能で補足することが重要です。
こうした記述によって、AIにも“根拠のある信頼性の高い情報”として認識されやすくなります。
?AIは“文脈”で理解する
生成AIは、単語単位ではなく文脈全体を読み取りながら、意図や意味を判断しています。
そのため、「高品質」「安心設計」「最先端」といったあいまいで広告的なフレーズは、情報としての評価対象から外れる可能性もあります。
重要なのは、“ユーザー視点で納得できるかどうか”という基準でコンテンツを見直すことです。
AIに最適化するとは、テクニックではなく、読み手にとって本当に役立つ情報を丁寧に届けることが第一です。
ステップ2:カテゴリーページを“情報ページ”へ進化させる
商品を並べるだけのリスト型カテゴリーページも、GEOの視点では再設計が不可欠です。
単なる一覧表示から脱却し、ユーザーとAIの双方にとって“意味のある情報ページ”へとアップグレードする必要があります。
そのためには、下記のような要素をページ内にしっかりと組み込むことが求められます。
【カテゴリーページに盛り込むべき要素】
| 要素 | 役割・目的 |
|---|---|
| カテゴリー定義 | なぜこのカテゴリー分類が存在するのか、どのようなニーズや目的に応えるものなのかを説明する |
| 選定基準 | このカテゴリに含まれる商品が、どのような基準・観点で選ばれているかを明示する |
| 用語解説 | 製品のUSP(独自の強み)や主要なフィーチャー(機能)に関する専門用語の意味をわかりやすく解説する |
| FAQ(よくある質問) | 該当カテゴリ内でよく寄せられる質問とその回答を掲載し、ユーザーの疑問を事前に解消できるようにする |
加えて、スキーママークアップ(Schema.org)を活用することで、ページの文脈や構造をAIが正しく理解できるようにしましょう。
また、関連コンテンツとの内部リンクも、論理的な階層構造に沿って整理することで、ユーザー体験の向上とAIによる評価の両立が期待できます。
ステップ3:テクニカルSEOを“AI視点”で再強化
GEO時代においても、テクニカルSEOはマーケティング基盤として引き続き重要な役割を担います。
中でもスキーママークアップ(構造化データ)の実装は、単にリッチスニペットの表示を狙うためのものではなく、AIがコンテンツの構造や意味を正確に理解・分類するための“共通言語”として機能する手段なのです。
【必須の構造化データ項目】
- 商品情報:ブランド名、価格、レビュー、在庫状況などの基本情報
- サイト構造:パンくずリスト、FAQページ、組織情報などのスキーマ
- AIクローラーのアクセス許可(必須):GPTBot、ClaudeBot、PerplexityBotなどのAIクローラーがサイトにアクセスできるよう、robots.txで明示的に許可
テクニカルSEOを強化することで、Webサイトの信頼性が高まり、AIに参照される可能性も向上します。
逆に、どれだけ優れた構成やコンテンツを用意しても、AIクローラーがアクセスできなければGEOの効果は発揮されません。この点はぜひ押さえておきましょう。
実務ガイド②コンテンツ構成における“新しい原則”
コンテンツの構成においては、「質問」を起点とした循環型の構造を取り入れることが重要です。
単なる情報の羅列ではなく、「質問 → 背景の説明 → 実際の事例 → 要点の整理 → 次のアクションの提案」という一連の流れに沿って構成するのが理想的です。
特にECコンテンツにおいては、冒頭でユーザーの疑問に直接答える構成(AEO:Answer Engine Optimization)を取り入れたうえで、その後にGEOの観点から、文脈や具体的な活用事例を丁寧に補足する流れが効果的です。
?コンテンツ構成の具体例(EC向け)
質問:「ワイヤレスヘッドホンを選ぶ際に、重要な基準は?」
即答(AEO):「ノイズキャンセリング、バッテリーの持続時間、装着感が重要」
詳細説明(GEO):それぞれの基準について、具体的な事例や統計データを用いて解説する
「長いページを、誰が読むのか?」という声もあるかもしれませんが、今やコンテンツの“読者”は人間だけではなく、検索クローラーや生成AIでもあります。
「人 × クローラー × AI」に対して同時に最適化されるべきなのです。
実務ガイド③マルチプラットフォームでの“コンテンツ流通設計”
ECにおけるSEO/GEO統合戦略は、単にコンテンツを作るだけでなく、“どこで届けるか”という流通チャネルの設計も同じくらい重要です。
なぜなら、AIは企業の公式サイト(D2Cサイト)上のコンテンツだけを参照しているわけではないからです。
では、AIはどこから情報を学習しているのでしょうか?
それは、Reddit、Quora、Medium、YouTubeなどに投稿された、ユーザー生成コンテンツ(UGC)やブランドに関する言及です。これらが、AIにとっての“参考資料”になっています。
つまり、製品レビューや使用事例といったコンテンツは、自社サイトだけに留めず、外部プラットフォームにも積極的に展開する必要があります。さらに、ユーザーとのやり取りを通じて、自然なレビュー投稿やブランド言及を促す仕組みをつくることが、GEOの観点では非常に効果的です。
?統合型コンテンツエコシステムの構築
■ SEOとGEOは「つなげて考える」のが基本
最も重要なのは、SEOとGEOをバラバラに考えるのではなく、ひとつの有機的なコンテンツシステムとして管理することです。
EC企業にとって大切なのは、コンテンツ制作・配信・構造設計といったすべての要素を連動させ、統合的に運用できる体制をつくることにあります。
■ テキスト以外のコンテンツも重要
さらに、コンテンツはテキストだけにとどまらず、画像・音声・動画など、複数の形式で展開することも意識しましょう。
そして、それぞれのコンテンツ形式に対しても、AIが理解できるように構造化(例:Altテキストやメタデータの整備)しておくことが大切です。
まとめ:SEOの再定義、そしてGEOという次の一手
検索結果ページは今や、リンクの羅列から“AIによる即答”へと進化しています。
こうした変化の中で、SEOは終わったのではなく、新たな役割へと進化し続けているのです。
今後、企業が目指すべきは「AIがユーザーに最初におすすめするブランド」となること。
そのためには、AIが真っ先に参照し、正確に理解できるコンテンツ資産を、継続的に積み上げていくことが不可欠です。
【これからのコンテンツ資産に必要な要素】
- 消費者インサイトに基づくトピック設計(関心テーマ・購入意図)
- 構造化されたデータと自然言語による文脈
- 他にはない独自の事例や顧客体験
- スペックやベンチマークなどの比較情報
SEOは終わったのではなく、時代の変化にあわせてその役割を再定義しつつあります。
かつてはAEOを取り込み、ユーザーの質問に答える方向へと進化してきましたが、今はさらにGEOを取り込み、AIとともに新たな情報エコシステムを築くフェーズへと移行しています。
この変化は終わりではなく、新たな始まりなのです。
おすすめ記事
・AEOとは?ゼロクリック時代に“答え”を届ける検索戦略【生成AI時代のSEO再定義】
・GEOとは?AIに学ばせる新しいSEO戦略とAEOとの統合アプローチ【生成AI時代の検索最適化】
この記事のタグ