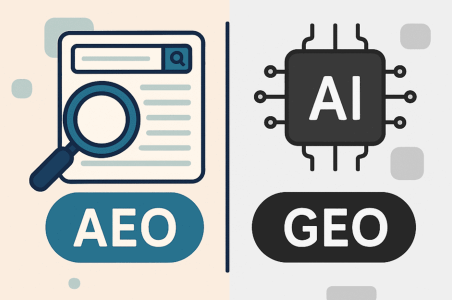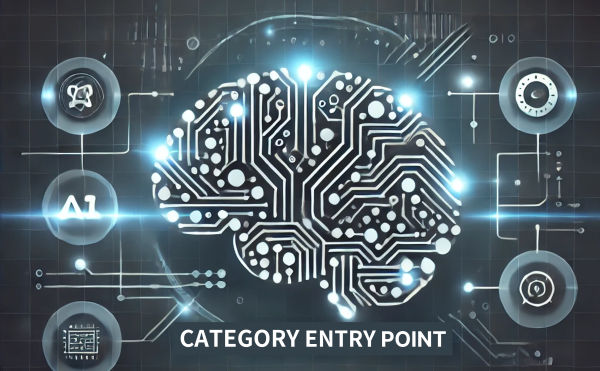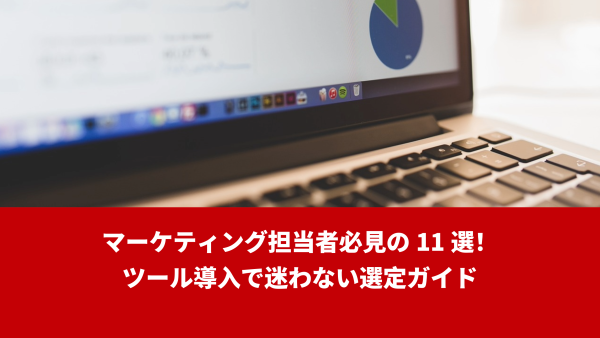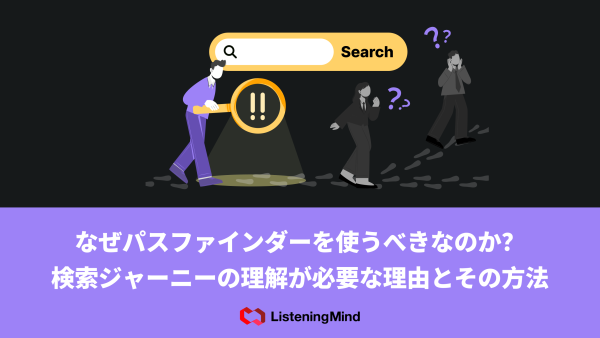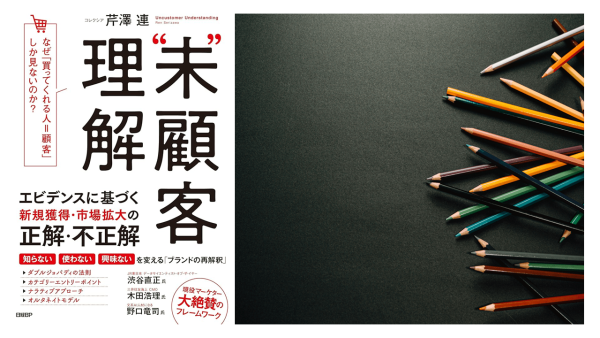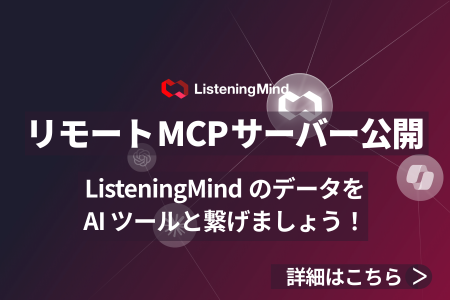2025年、検索環境は“再定義”のフェーズへ
2025年、検索を取り巻く環境が大きく変わり始めています。
従来の「Google検索で上位表示を狙うSEO戦略」だけでは、ユーザーの変化に追いつけない時代になりました。
ChatGPTやPerplexity、GoogleのAI Overviewsといった生成AI型の検索ツールが普及したことで、ユーザーは“リンクを選ぶ”のではなく、“AIが生成した答え”を受け取ることを前提とした検索行動へとシフトしています。
これからの検索戦略において、AEOとGEOをどう理解し、どう組み合わせて活用すべきか──そのヒントを2部構成でお届けします。
本記事では、まずはAEO(Answer Engine Optimization)に焦点を当て、「ゼロクリック時代」にブランドがどのように“答え”を提示すべきかを整理します。
後編では、検索行動の進化とともに台頭してきたもうひとつの重要な概念、GEO(Generative Engine Optimization)について詳しくご紹介します。
AEOとGEO──マーケターが“今”注目すべき2つのキーワード
こうした検索体験の再定義が進む中、マーケターの間で急速に注目を集めているのが、AEO(Answer Engine Optimization)とGEO(Generative Engine Optimization)という2つの概念です。
一見すると似た意味で語られることもありますが、実際には検索構造とユーザー行動の変化に対応した、まったく異なる戦略的アプローチを意味しています。
検索結果に“答え”を出すことを目的とするAEOと、AIの“学習対象”となることを目指すGEO。これらを正しく理解し、戦略的に使い分けることが、これからのSEO・コンテンツ戦略において極めて重要になっています。
AEOとGEOの違いまとめ|生成AI時代のSEO比較
| 項目 | ? AEOコンテンツ | ? GEOコンテンツ |
|---|---|---|
| 目的 | 即答の提供(強調スニペットを狙う) | 知識の内在化(AIモデルにブランド知識を学習させる) |
| 長さ | 短く簡潔(50〜100文字での回答) | 長く丁寧な記述(深い考察と分析) |
| 構造 | 質問中心+Schema活用(FAQやHowTo構造) | 事例・比較・統計・フレームワーク(Executive Summary+インサイト) |
| フォーマット | FAQやリスト形式(箇条書き・テーブル構造) | ナラティブ中心(深みのあるストーリー構成) |
AEOとは?“検索で答えを出す”ためのコンテンツ最適化
AEOとは、ユーザーの質問に対して「簡潔で直接的な答え」を提示することで、Googleの強調スニペットやPAA(People Also Ask)といった“答え枠”への掲載を狙う戦略です。
このアプローチは、Googleが2014年に本格導入した強調スニペット機能をきっかけに注目され始めました。検索クエリの意図が明確で、短い一文で答えられるような質問に対し、Googleは単一ページから情報を抜き出し、検索結果の最上部に表示します。
つまり、「クリックされること」を目的とした従来型SEOから、「検索結果内で完結させる回答提供型SEO」へと進化しているのです。
AEOが機能する領域と実際の成果
AEOは特にスマートフォン利用が中心のモバイル検索や、音声検索との相性が良く、ユーザーの“すぐに知りたい”ニーズに応えるため、多くのブランドがこの領域でのコンテンツ最適化に取り組んできました。
たとえば企業FAQやヘルプページ、Q&A型の製品紹介ページなどは、構造化と文体を最適化することで「0番目の結果(Position Zero)」への掲載を目指すことができます。
AEO施策に成功したコンテンツは、短期間でトラフィックを大きく伸ばした事例も少なくありません。ブランド認知の初期加速やFAQ型クエリに対する対応力強化という観点で、この10年間でSEO戦略の中核を担ってきたアプローチのひとつといえるでしょう。
AEOのデメリットとゼロクリック問題とは?
便利さゆえに注目を集めてきたAEOですが、その構造的な特性ゆえに明確な限界も存在します。
AEOの要となる強調スニペットは、あくまで“答え”を単体で抽出して表示する仕組みです。そのため、ブランドが提供する文脈・専門性・独自視点がカットされてしまうケースが少なくありません。
さらに、ユーザーが検索結果をクリックせずに完結してしまう「ゼロクリック現象」も深刻化しています。
スニペットで答えが得られれば、その先のサイトへは訪問しない。
つまり、コンテンツを見てもらえず、ブランドが伝えたいことが届かないという課題に直面するのです。
?参考データ
SparkToroのCEOであり、Moz創業者でもあるランド・フィッシュキン(Rand Fishkin)氏の2024年の調査によると、米国Google検索の58.5%がクリックなしで終了しており、特にモバイル検索においては77.22%がゼロクリックであったという結果が報告されています。
それでもAEOは有効─「可視性」を高める戦術としての価値
とはいえ、AEOは検索上での可視性を高めるうえで、今も有効な施策です。
特に以下のような文脈においては、今も高い成果が期待できます。
- 音声検索(Voice Search)による即時回答ニーズ
- PAAなど質問連鎖型検索の対応
- FAQコンテンツへのアクセス導線の強化
これらの領域では、「検索で答えを探す」ユーザーのニーズとAEOの設計が一致しているため、トラフィック誘導以上の意味を持ちます。加えて、コンテンツ構造化に関する技術的ノウハウもすでに確立されており、導入のハードルも比較的低いのが特徴です。
?AEO施策におけるコンテンツ最適化のベストプラクティス
- 導入部で結論ファースト:冒頭に50〜100文字で要点を明示する
- H2・H3の見出しで構造化:質問形式でセクションを整理
- リスト・表・箇条書きを活用:視認性と抽出性を高める
- Schema.org対応:FAQページ/QAページ/HowToなどの構造化マークアップを設定
まとめ
AEOは、ユーザーの検索体験に瞬時に“答え”を届けるうえで有効な戦略です。
しかし、「情報を届ける」ことと「知識としてAIに学ばれる」ことは、似て非なるアプローチです。
後編では、検索戦略の次なる進化系であるGEO(Generative Engine Optimization)について詳しく掘り下げていきます。
AIが生成する回答の中で、いかに自社コンテンツを“学習対象”として定着させていくか──その鍵を握るGEOの全貌に迫ります。
この記事のタグ