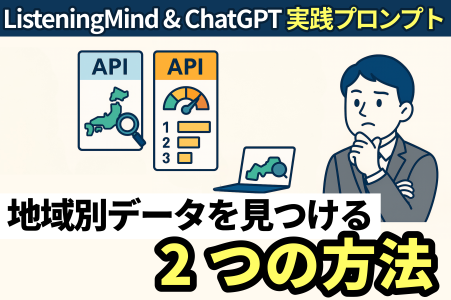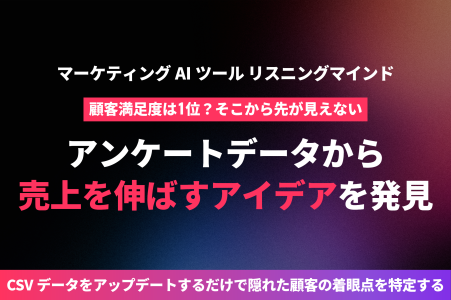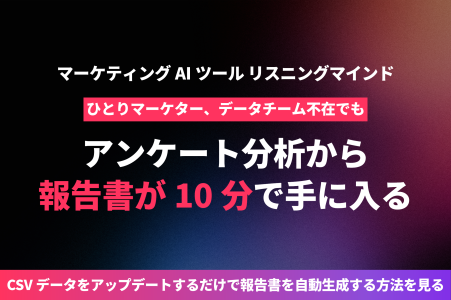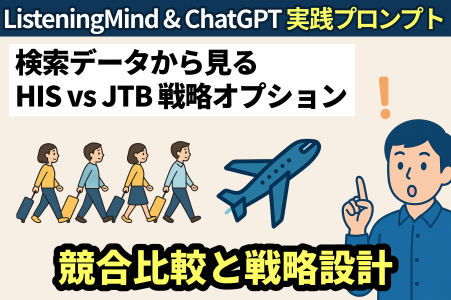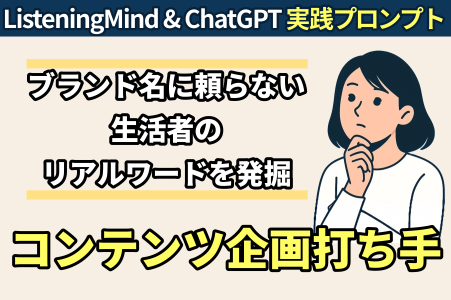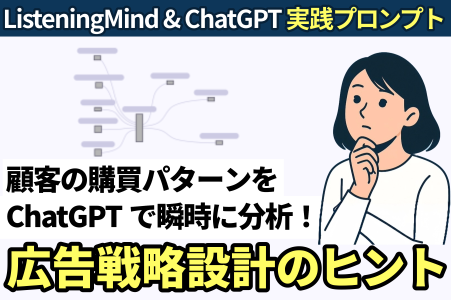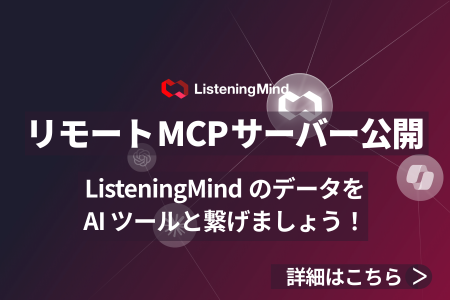ListeningMind & ChatGPTを通じて、検索ボリュームなどの地域別データを取得することができます。しかし、その方法は2つあります。1つは「GoogleトレンドAPI」を使用する方法、もう1つは「Google広告API」を使用する方法です。
両APIとも地域別のデータを提供しますが、違いがあります。Google広告APIを使用すると、地域別の定量的な検索ボリュームを取得できます。一方、GoogleトレンドAPIを使用すると、具体的な数値ではなく、0から100の範囲で示される相対的な関心度データを取得できます。
2つの方式による違いは以下の通りです。
| 区分 | Google広告API | GoogleトレンドAPI |
| データタイプ | 実検索ボリューム(件単位) | 検索インタレスト指数(0~100、相対値) |
| 期間選択 | 最大48ヶ月(月単位の時系列提供可能) | 1日~5年単位で自由に選択可能 |
| 地域分析の方法 | 特定のロケーションに対して数値を提供 | 複数地域間の相対比較が可能 |
| 活用目的 | 正確な地域別検索ボリュームの把握 | シーズナリティ分析、急上昇地域の検知 |
| 表現方法 | 数値(例:3,600件) | 0~100の範囲(例:東京100、大阪75) |
では、2つの方式をそれぞれプロンプトで実行してみましょう。まずはGoogle広告APIを使用したプロンプトです。
オリオンビール - 日本の都道府県全体(47都道府県)の検索ボリュームデータを収集して。必ずGoogle広告APIでロケーションのリストを確認した後、都道府県別に繰り返し呼び出して。
このデータをもとに、日本の地図に検索ボリュームを可視化したHTMLマップも作成して。この時、重要なのは必ず「Google広告APIでロケーションのリストを確認した後」という一文を入力することです。これにより、GPTが混乱することなく、ユーザーの意図を正確に理解します。リスニングマインドのAPI通信を開始する段階で、以下のような確認画面が表示されます。「確認」をクリックします。
収集が始まります。しかし、APIの仕様上、1回の実行で1つの地域のデータしか収集できません。そのため、以下のような応答が表示されます。
したがって、ユーザーは毎回「続けて」のような簡単な指示を入力する必要があります。(もちろん、「。」のような記号だけでも構いませんが、少し手間がかかります)
検索ボリュームの収集がすべて完了した後、”このデータをもとに、日本の地図に検索ボリュームを可視化したHTMLマップも作成して” プロンプトで可視化すると、以下のように地図上に各検索ボリュームが表示されます。
やはり沖縄県の検索ボリュームが高いですね。東京都が月間12,100件で最も多く、沖縄県が2番目に月間8,100件の検索ボリュームを示しています。
次に、2つ目の方法であるGoogleトレンドAPIを使用する方法です。
オリオンビール - 日本の都道府県全体(47都道府県)の2025年5月の関心度データを収集して。必ずGoogleトレンドAPIでロケーションのリストを確認した後、収集して。この方式も同様に、1回の実行で1つの地域しか収集できないため、少し時間がかかります。結果は以下のように出力されます。
| 都道府県 | 2025年5月の関心度 | 意味 |
| 東京 | 78.5 | 東京での過去12ヶ月間のピーク時に対し、5月の検索関心度が78.5%の水準 |
| 大阪 | 66.75 | 大阪での過去12ヶ月間のピーク時に対し、5月の検索関心度が66.75%の水準 |
| 沖縄 | 65.25 | 沖縄でも同様に高い関心度を示している |
まとめ
ListeningMind & ChatGPTを通じて地域別の検索データを取得するには2つの方法があります。1つは「GoogleトレンドAPI」、もう1つは「Google広告API」です。
- GoogleトレンドAPIは、「いつ検索が急増/減少したか」「季節性のあるキーワードか」「同じキーワードの地域間での相対的な関心度」を把握したい場合に使用します。
- 定量的な検索ボリュームの数値が必要な場合は、「Google広告API」を使用すると良いでしょう。
オリオンビール - 日本の都道府県全体(47都道府県)の検索ボリュームデータを収集して。必ずGoogle広告APIでロケーションのリストを確認した後、都道府県別に繰り返し呼び出して。
このデータをもとに、日本の地図に検索ボリュームを可視化したHTMLマップも作成して。※ 本記事は、検索データに基づく分析事例であり、特定のブランドや製品のマーケティング戦略を代弁または評価することを目的としたものではありません。
使用されているキーワードは、実際の検索ボリューム、サジェスト、関連検索語などの情報をもとに収集されたものであり、消費者の関心や情報探索パターンを理解するための分析例として提示しています。
記載されているブランド名および製品は、分析構造を説明するための事例として引用しており、各企業の公式な見解や実際の施策とは関係ありません。
本文の内容は筆者個人の見解に基づくものであり、誹謗中傷、歪曲、営利目的は一切含まれておりません。