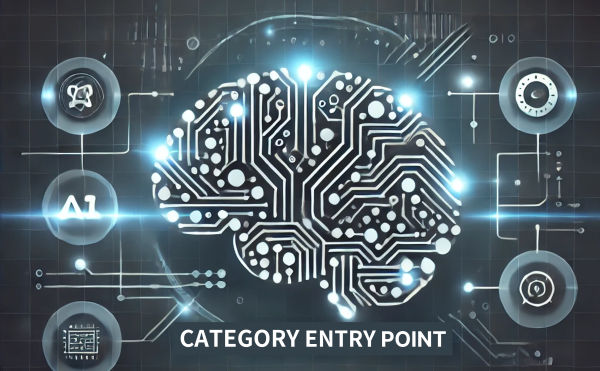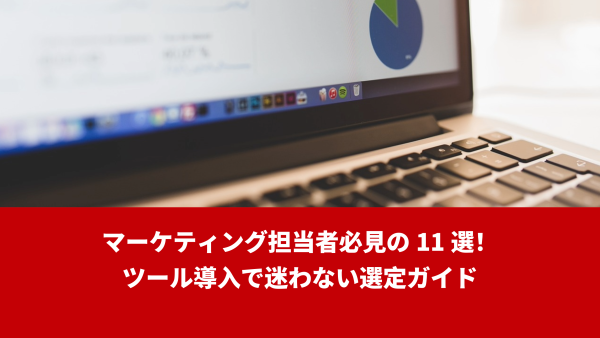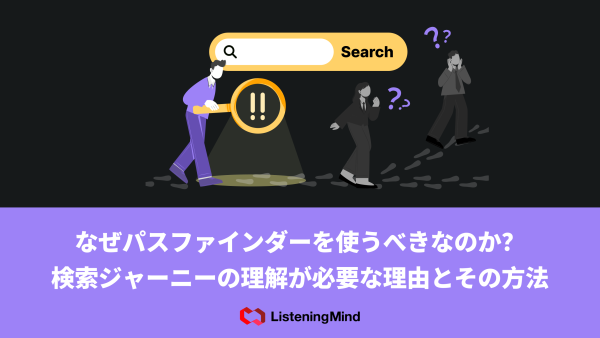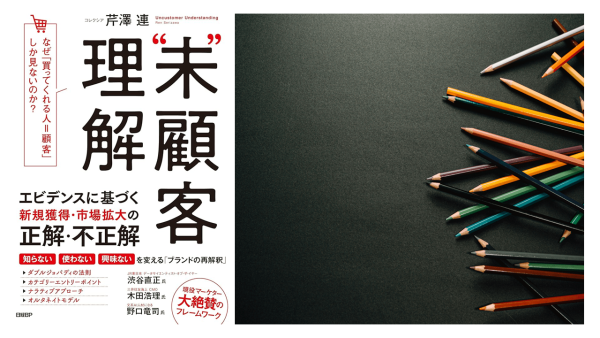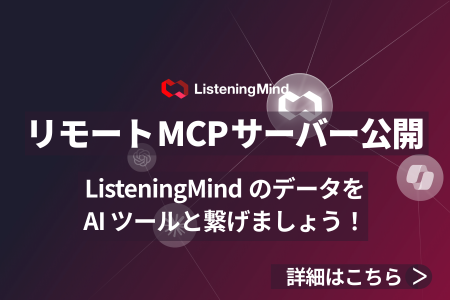前回の記事では、リスニングマインドを活用して、消費者の検索ジャーニー上のあらゆる接点に広告を届ける方法を紹介しました。
一方で、検索広告だけを“検索マーケティングそのもの”と捉えてしまうと、多くのブランドが成果の伸び悩みに直面します。
今回の記事では、実際の広告運用担当者が現場で直面している検索広告の限界を起点に、検索マーケティングをより広い視点で捉えるための新しいアプローチをご紹介します。
アプローチを変える
検索広告を運用した経験のあるマーケターなら、きっと一度はこんな状況に直面したことがあるはずです。
- 広告配信で流入は増えているのに、コンバージョンがほとんど発生しない
- 成果が出るのは自社名キーワードだけで、一般キーワードでは売上につながらない
多くのブランド担当者は検索広告の運用を代理店に任せています。そして代理店からは、CTR(クリック率)やCPC(クリック単価)などの指標を用いて、流入効率や広告費に対する売上効率(ROAS)といったレポートが届けられます。
一見するとROAS が良好に見えても、実際にデータを深掘りすると自社名キーワード以外では売上がほぼ発生していない というケースは珍しくありません。特にこの傾向は、ブランド認知の低い新興ブランドや中小企業で顕著です。
こうした状況で代理店に“一般キーワードではコンバージョンが起きない”と相談すると、返ってくる答えは概ねこうです。
「LPを改善した方がいいと思います。」
これはつまり、検索広告の役割は“流入”であって、“コンバージョン”は広告ではなく LP の役割という考えに基づいています。しかし、この考え方は半分正しく、半分間違っています。
■ なぜ一般キーワードで売上が出ないのか?
ブランド認知が高い企業であれば、消費者はすでにブランドを知っており、信頼度も高いため、広告から流入した後のコンバージョン率も高くなりやすいです。
一方、ブランド認知が低い企業では事情が異なります。
入札単価を上げて広告順位を 1 位にしたとしても、“ブランドそのものの信頼” が育っていないため、ユーザーは興味は持ってもすぐに離脱し、他のブランドを比較しにいってしまうのです。
ここで多くのブランドが悩みに直面します。
- 自社名キーワードだけ運用していても、売上は増えないし、新規顧客も広がらない。
- 一般キーワードを配信すれば、流入は増えるものの費用ばかりかかって成果が出ない。
このジレンマに陥ったとき、多くのブランドは「広告の最適化」や「LP改善」の方向に意識が向きがちです。しかし、ここで必要なのは、視点そのものを変えることです。
「どうすれば検索広告で売上が出るか?」
↓
「どうすれば消費者の検索行動の中に、自社ブランドを継続的に露出させ、
認知と信頼を強化できるか?」
このようにアプローチを変えるだけで、見えてくる世界が一気に広がります。
検索広告だけに頼るのではなく、“消費者の検索行動にブランドを自然に溶け込ませていくアプローチ”へ視点を切り替える必要があります。
SERPのシェア率を高める
SERP(Search Engine Results Page)とは、ユーザーが検索した際に表示される検索結果ページのことです。オフラインでたとえるなら、店頭の陳列棚のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
皆さんはお店に入った瞬間、まずどのブランドが目に入りますか?
- 入口のすぐ近くに陳列されているブランド
- 最も大きな売り場スペースを持っているブランド
多くの場合、この2つに目が行くのではないでしょうか。
これを検索マーケティングに置き換えると、次のようになります。
- 入口付近のブランド → 上位表示されたコンテンツ
- 広い売り場を持つブランド → SERPシェア率の高いブランド
つまり、検索結果の中で “どれだけ多くの枠を押さえているか” が、ブランド認知や接点構築に大きく影響するわけです。
では、Google の SERP がどのように構成されているかを見てみましょう。
今回も前回と同じく“ビタミンC”というキーワードを例に確認します。

上の図からわかるように、Google は 情報の形式に関係なく、検索意図に最も合致するコンテンツを優先的に上位表示 します。
そのため、同じビタミンC関連でも、
・ビタミンC 効果
・ビタミンC 過剰摂取
・ビタミンC サプリ 比較
など、キーワードによって検索意図が異なるため、表示されるコンテンツの種類や順序も異なります。
また、図を見てもわかる通り、広告が占める割合は決して多くはありません。
ユーザー視点で考えてみましょう。
特定のブランドが頭に浮かばない状態で検索する場合、多くの消費者は広告だけでなく、検索結果に表示されるさまざまな情報源(記事、比較ページ、Q&A、動画など)を確認します。
特に情報型キーワードになればなるほど、ユーザーは広告よりコンテンツの方に注意を向ける傾向があります。
そして、検索結果ページに表示されるコンテンツ数には限りがありますが、もしその限られた枠の中に自社のコンテンツが一つずつ広く配置されていれば、ユーザーは自然と自社ブランドを繰り返し目にし、認知・理解が深まります。
これこそが SERPシェア(検索結果占有率)を高める意義 です。
したがって、広告だけでなく “コンテンツ領域を広げる”=SEO対策 が次に必要になります。
その前にまず、SEOを行う上で前提となる検索エンジンの特徴を整理しておきましょう。
検索エンジンの構成
Googleのように検索エンジンと呼ばれるサービスには、基本的に次の3つの機能が備わっています。

クロール(Crawling):ページを集める
クロールとは、インターネット上に存在する膨大なページをくまなく収集するプロセスです。
この収集作業を担うソフトウェア(ボット)のことを クローラー と呼びます。
クローラーは、リンクをたどりながら世界中のページを巡回し、情報を持ち帰ってきます。
SEOの入口は、このクロールしてもらえる状態を作ることから始まります。
インデックス(Indexing):テーマごとに整理する
クローラーが集めてきたページは、検索エンジン内部でテーマ別に整理(インデックス化)されます。
これは、書店や図書館で本が「人文」「科学」「文学」といったジャンルに分かれて並ぶのと同じ仕組みです。ユーザーがミステリー小説の棚から本を探すように、検索エンジンも 関連性の高いテーマの中でページ同士を比較 しています。
重要なポイントは、検索エンジンは全てのURLを平等に扱うということです。
そのため、昨日作ったばかりの新しいページも、何年もアクセスがあり続けている有名サイトも、どちらも同じテーマの中での勝負になります。
だからこそ、しっかり作り込まれた1つのコンテンツが突然上位に躍り出ることも、複数のキーワードで上位表示を獲得することも十分に起こり得ます。
ランキング(Ranking):順位づけして検索結果に表示する
最終ステップがランキングです。インデックス化されたページを、ユーザーの検索意図に合わせて順位づけし、検索結果として表示します。マーケターが言う“上位表示”は、このランキングを指しています。
かつては、キーワードを不自然に詰め込むなどの小手先テクニックで上位を狙うこともできました。
しかし現在は、そうした手法は一切通用しません。
Googleでは、ユーザーにとって有益・必要な情報が整理されている・読みやすく信頼性の高いコンテンツのような、 “本当に価値のある情報” が上位に表示されるようになっています。
そのため、短時間で大量に作られた機械的なコンテンツはすぐに順位が下落し、丁寧に作られた高品質なコンテンツだけが残る時代になっています。
重要なのは“検索意図”の理解
検索エンジンは、入力されたキーワードが多少異なっていても、ユーザーが求めている“意図(インテント)”が同じだと判断すれば、同一または類似のコンテンツを表示します。
誤字があっても、曖昧な表現でも、ユーザーが探している情報に辿り着けるのはこの仕組みのおかげです。
つまり、検索結果で最も重視されるのは、そのページがユーザーの検索意図をどれだけ満たしているかという一点に尽きます。
この前提に立つと、マーケターが検索マーケティングを設計する上で最も重要なのは、
・ユーザーはどんな背景や課題を持ってそのキーワードを検索したのか
・なぜその言葉を選んだのか
・検索した結果、何を知りたいのか/何を解決したいのか
といった“検索の裏側にある意図”を正確に読み解くことです。
この意図が理解できていなければ、広告クリエイティブも、コンテンツも、ユーザーの心には届きません。
逆に言えば、検索意図さえ深く理解できていれば、“広告でどんな訴求を出すべきか・どのテーマでコンテンツを作るべきか・どんな導線が最適か”といった判断がクリアになり、検索マーケティング全体の精度が大きく向上します。
まとめ
本記事では、検索マーケティングに取り組む際にまず押さえるべき考え方として、
・どのようなアプローチで検索マーケティングを設計すべきか
・検索エンジンはどのような仕組みでページを評価しているのか
・そして今後 SEO を進める上で意識すべきポイント
について整理してきました。
これらの理解が深まると、広告・SEO といった施策の“点”ではなく、ユーザーの検索行動全体を見据えた“線”としての戦略設計が可能になります。
次回の記事では、リスニングマインドを活用してより効果的・効率的に SEO マーケティングを実践する方法 を紹介し、実際のブランドがどのように成果を出しているのかもあわせて解説していきます。
【おすすめの記事】
この記事のタグ