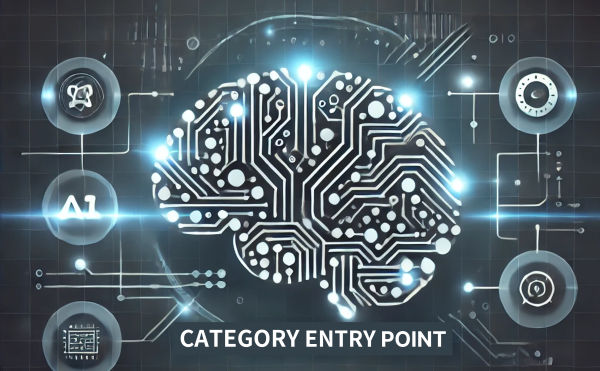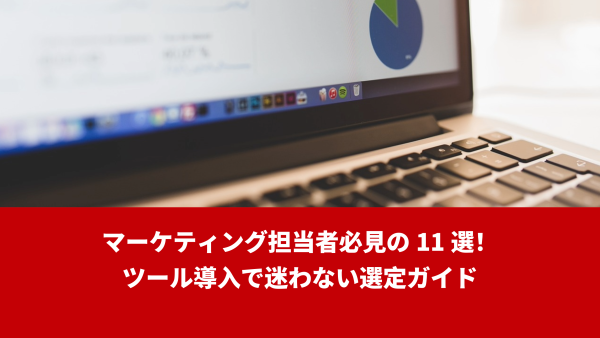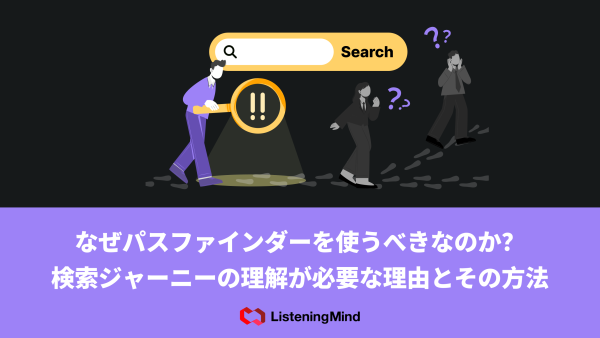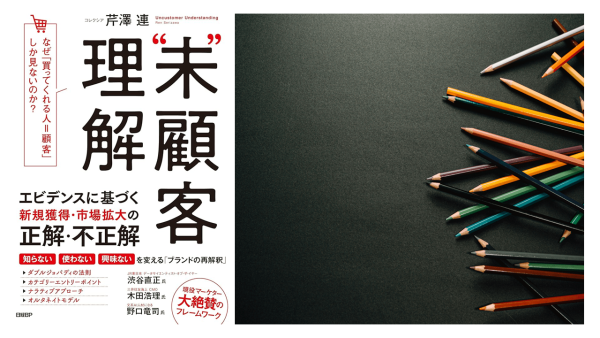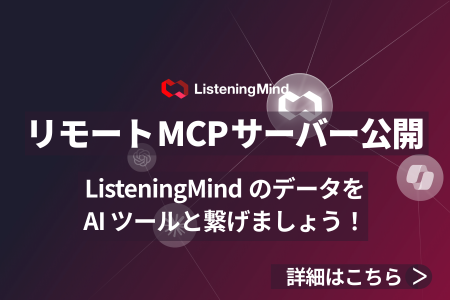検索広告を運用しているマーケターなら、Googleキーワードプランナーをはじめとしたキーワードツールを日常的に活用しているはずです。広告設定の出発点となる“キーワード発掘”に欠かせない存在ではありますが、実際の運用現場では“時間がかかる・抜け漏れが出る・属人的になりやすい”など、限界を感じることも多いのではないでしょうか。
本記事では、実際に広告運用担当者が活用している“検索広告の成果を高めるための具体的な使い方” を、詳しく紹介していきます。
従来の検索広告運用の限界
従来の検索広告運用は、一見ロジカルに見えるものの、実際には多くの属人的な判断や作業に支えられており、構造的な課題を抱えています。
1.マーケターの経験・スキルに過度に依存している
まず、キーワードプランナーは「入力されたキーワード」を起点に関連ワードを提示する仕組みであるため、発掘できるキーワードの範囲がどうしても限定的になります。
そのため、検索ユーザーが実際に使う多様なキーワードを的確に拾い上げるためには、マーケター自身の経験値や想像力に強く依存せざるを得ません。経験豊富な担当者でなければ、潜在的な検索語を網羅的に入力することは難しく、結果として設定の質が担当者によって大きく変わってしまいます。
つまり、同じ商材であっても、誰が運用するかによってキーワード戦略の深さや広がりに大きな差が生まれてしまうという構造的な課題が存在するのです。
2.キーワード分類(キャンペーンセット)に膨大な時間がかかる
次に、キーワード分類作業にかかる手間と工数の大きさが挙げられます。
Google広告ではキーワードごとの個別入札ができないため、テーマや意図ごとにキーワードを整理し、適切にグルーピングしてセット運用することが不可欠です。自動のグルーピング機能はあるものの精度に限界があるため、結局は担当者が手作業で再分類し、細かく構築し直す必要があります。
結果として、キーワード分類は運用者の時間を最も奪う作業の一つとなり、本来注力すべき戦略設計や改善施策に割ける時間を圧迫してしまうという問題が発生します。
3.見落としている市場が存在する
さらに、Googleのキーワードツールは「検索量」や「入札競争度」といった定量データを中心に構成されており、実際の検索意図や検索行動の流れまでは十分に反映されません。
このため、数字だけを基準にキーワード戦略を組み立てると、顕在的なトラフィックは取れても、需要の兆しや新しい検索行動といった“定量化されにくい市場”を見落としてしまうリスクがあります。
その結果、ブランドにとって重要な顧客接点を取りこぼし、機会損失につながる可能性が高まります。
このように、従来の検索広告運用には明確な限界が存在します。
従来の広告設定作業
理解しやすいように、ここでは日々の実務で起こり得る状況を想定してみましょう。
▶想定状況:最近入社した健康食品メーカーで、ブランド認知が低いビタミンCサプリの検索広告を設定する必要がある。
▶一般的な業務の進め方:
- Google キーワードプランナーで“ビタミンC サプリ”の関連キーワードを抽出
- 数百件のキーワードをExcelにダウンロード
- まずはキーワードをひとつずつ確認し、テーマごとに分類
- キーワード拡張のため、分類したキーワードを基点に、再度関連キーワードを抽出
- 抽出 → 分類 → 再抽出…という作業を繰り返す
キーワード数が多いほど、収集・分類・拡張のループが止まらず、気付けば同じ作業を何度も繰り返している状態に陥ります。
ここで疑問が生まれます。
なぜ、私たちはキーワードの収集と分類をこんなにも繰り返さなければならないのでしょうか?
その理由は、消費者が実際にどんな言葉で検索しているのかという基礎データが手元にないまま作業を始めているからです。
基礎知識がなければ、自分の頭に思い浮かぶワードや、商品名に関連しそうなワードから手探りでキーワードを広げていくしかありません。
しかし、これは 地図を持たずに知らない街を歩き回り、目的地を探す行為 とほとんど同じです。
効率が悪く、抜け漏れも多く、時間だけが過ぎていきます。
では、マーケターはどうすれば消費者の目的を正確に捉え、効率よくキーワードの分類・設定を行い、キャンペーン設計をより効果的に行えるのでしょうか?
リスニングマインドを活用した、新しい広告運用戦略
STEP 1. パスファインダーで消費者の検索行動を把握する
検索広告の設定で、最初に取り組むべきことは何でしょうか。
多くの方がキーワード選定と答えるかもしれません。
しかし、本当に最初に行うべきは、消費者の検索行動(検索ジャーニー)を理解することです。
ユーザーがどんな悩みや目的から検索を始め、どんなキーワードを経由し、最終的にどのブランド・製品へたどり着くのか。
この一連の流れを把握してはじめて、広告を“最適なタイミング”と“最適な接点”で届けることが可能になります。
パスファインダーに“ビタミンC”や“ビタミンC サプリ”といったキーワードを入力すると、それらを検索したユーザーの前後の行動が、検索経路として可視化されます。


このデータを見ると、ユーザーが“ビタミンC”というキーワードで検索する際には、効果・摂取量(過剰摂取)・美容効果など、さまざまなテーマに関心を持っていることがわかります。この段階で、すでに広告セットに活用できるカテゴリが自然と浮かび上がってきます。
さらに、検索行動の終点を見ていくと、特定のブランド名や製品タイプが現れます。これにより、現在どのブランドが市場で存在感を高めているのか、
そして 消費者がどんなタイプのビタミンを求めて検索しているのか といった洞察を得ることができます。
これまでビタミンC市場の消費者について知識がゼロであった担当者でも、わずか2つのキーワードを起点に検索経路を分析するだけで、消費者は何に関心を持ち、どのような経路で情報収集を行い、どのブランドへたどり着くのかを把握できます。
これは、まさに“ひとつの消費者マップ”を手に入れた状態です。次のステップでは、この消費者マップを活用して、
より精度の高いキーワード発掘へと進んでいきます。
STEP 2. インテントファインダーで膨大な関連キーワードを発掘する
STEP1でパスファインダーによって“全体マップ”が見えたら、次はインテントファインダーを使って、個々のキーワードについてより深く理解する段階に進みます。
インテントファインダーを活用すれば、従来のキーワードツールでは見つけることができなかった、新たな検索インサイトを発掘できます。
では実際に、“ビタミンC”というキーワードで検索してみましょう。(今回は美容液・化粧水などのコスメ系キーワードは除外しています)

検索量の推移は、6か月〜4年までの期間を指定して確認できます。
今回は検索広告の構築が目的であり、最も直近のユーザーニーズを把握する必要があるため 「直近6か月」 に設定してデータを分析します。
左側には、関連キーワードをテーマ別に自動分類した「トピック」が表示されます。
これにより、検索広告のクリエイティブにおいて、
どのユーザー層に、どんなメッセージを届けるべきか といった方向性まで明確に把握できるようになります。
さらに、インテントファインダーを活用することで、従来のツールでは抽出できなかった新たなカテゴリも浮かび上がってきました。
- 競合ブランドキーワード:ブランド名+ビタミンC
例:タケダ、dhc、ワカサプリ、リポなど
→ 月平均検索数:約11万件以上 - ビタミンC 摂取ガイドキーワード
例:摂取量、いつ飲む、飲むタイミング、飲み方、飲み合わせなど。
→月平均検索数:17,987件 - ビタミンC 肌関連キーワード
例:ニキビ、 シミ、毛穴など。
→月平均検索数:20,024件
パスファインダーとインテントファインダーの双方から収集したデータを基に、検索市場を次のように主要カテゴリへと整理することができます。
■ 整理されたビタミンC市場の主要カテゴリ一覧
- ビタミンC 効果(平均検索数:59,611件)
- ビタミンC 過剰摂取(平均検索数:16,188件)
- ビタミンC 肌(平均検索数:20,024件)
- ビタミンC 摂取ガイド(平均検索数:17,987件)
- ビタミンC おすすめ(平均検索数:26,355件)
- ビタミンC 競合ブランドキーワード(平均検索数:11万件以上)
もちろん、これらのカテゴリをもとにすぐに検索広告キャンペーンの構造を組むことも可能です。
しかし、ここでもう一歩踏み込み、まだ見落としているカテゴリがないか を確認しておくことが、より精度の高い広告戦略につながります。
次のステップでは、AIが自動分類したキーワードカテゴリと照合し、取りこぼしている潜在市場がないかどうかを明らかにしていきます。
STEP 3. クラスターファインダーでキーワードカテゴリを簡単に分類する
検索広告の運用において、最も時間を要する作業のひとつが、膨大なキーワードをテーマ別に分類し、広告セットを構築するプロセスです。
しかしクラスターファインダーを使えば、数千〜数万件のキーワードを、わずか数回のクリックで自動的に分類することができます。
下の画像は、“ビタミンC”というキーワードをクラスターファインダーで分析した際の画面です。
検索行動の前後にあたるキーワードを1〜3段階まで表示でき、クラスター名生成ボタンを押すだけで、AIがそれぞれのグループにわかりやすい名称を自動付与してくれます。

各グループを一目で確認するために「カードビュー」を選択してみましょう。
すると、下のようにグルーピングされた結果が表示されます。

生成されたクラスタの中には、これまで把握しきれていなかった新しいカテゴリ(黄色枠の部分)も含まれており、これらを広告戦略に追加することで、消費者の検索ジャーニー上のほとんどの接点で自社商品を露出させることが可能になります。
ただし、クラスタを細かく分ければ分けるほど、メッセージはより精緻になり、訴求の精度は上がります。
一方で、テーマの粒度を細かくしすぎると広告予算が分散し、十分な配信量を確保できず、かえって効果が出にくくなることもあります。
そのため 自社の広告予算や目的に応じて、どのレベルでセットを分割するのが最適なのかを見極めながら運用することが重要です。
小規模ブランド向け:検索広告運用で成果を出すためのTips
認知度がまだ低い小規模ブランドの場合、競争が激しい メインキーワード(=入札単価が高い領域)で広告を配信すると、費用だけが消化され、コンバージョンがほとんど生まれないケースが少なくありません。
限られた予算の中で成果が出ずに行き詰まってしまう...そんなときに有効なのが、次の 2つのアプローチ です。
直近伸びている低競合キーワードを狙う
インテントファインダーでは、直近3か月以内で検索量が増加している、かつ競合度の低いキーワード を抽出できます。
この増加傾向のキーワードをまとめて広告セット化することで、低い入札単価で露出を確保・新たな検索需要を先取り・一般キーワードより効率良くトラフィックを獲得といったメリットが得られます。
特にブランド認知がまだ弱いフェーズでは、“伸びているニーズ”に合わせて露出をつくることが最も効率的です。
広告では「露出」、SEOでは「信頼」を取りに行く
もし今の目的が 「コンバージョン」ではなく「露出確保」 であれば、メインキーワードの入札単価は 中〜下位に下げて運用しても問題ありません。
その代わりに、SEO向けの情報コンテンツ・比較記事・体験レビューや口コミ改善施策などを強化し、SERP(検索結果画面)全体でのブランド露出比率 を高める戦略が有効です。
ユーザーは、広告だけでなく記事・レビュー・Q&A・動画など複数のコンテンツを比較して判断します。
そのため、広告 × SEO × レビュー(UGC) の組み合わせが小規模ブランドにとって最も費用対効果の高い戦い方になります。
まとめ
検索広告とは、突き詰めれば消費者の心の動きを読み解くことそのものです。
単にいくつかのキーワードを抽出して配信するだけのアプローチでは、日々変化する検索行動や意図の流れを捉えることはできません。
そこでリスニングマインドは、従来のキーワードツールが抱える限界を補い、マーケターがより深く、より体系立てて戦略を構築できるよう支援します。
検索行動の流れ(ジャーニー)を理解する:パスファインダー
市場全体を立体的に俯瞰する:インテントファインダー
拡張キーワードや潜在ニーズを発見する:クラスターファインダー
これら3つのステップを組み合わせることで、単なる広告配信にとどまらず、消費者の検索意図に寄り添った、より精密で効果的なコミュニケーション設計が可能になります。
次回の記事では、検索広告を出してもコンバージョンにつながらないブランドが、検索マーケティングにどのように向き合うべきか、そしてリスニングマインドを活用することで検索広告だけではカバーしきれない領域をどのように克服できるのかについて解説していきます。
【おすすめの記事】
この記事のタグ