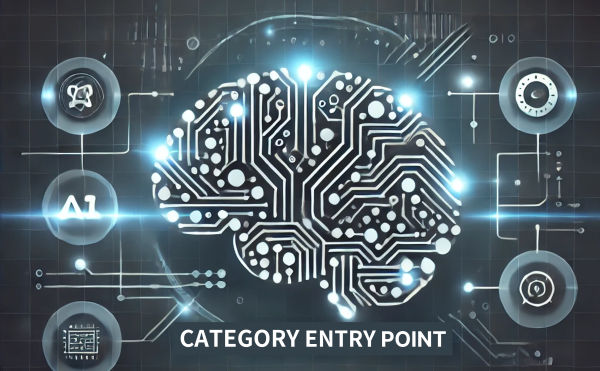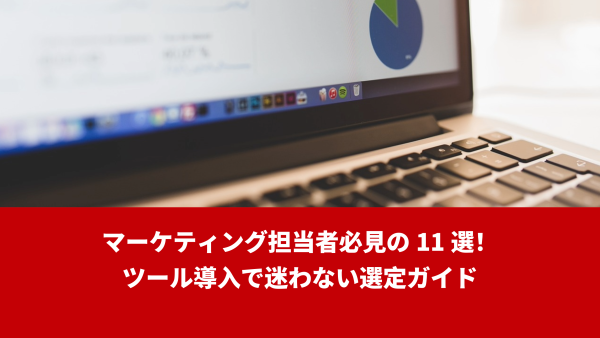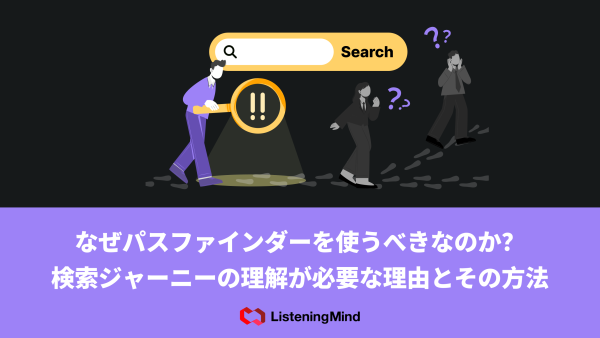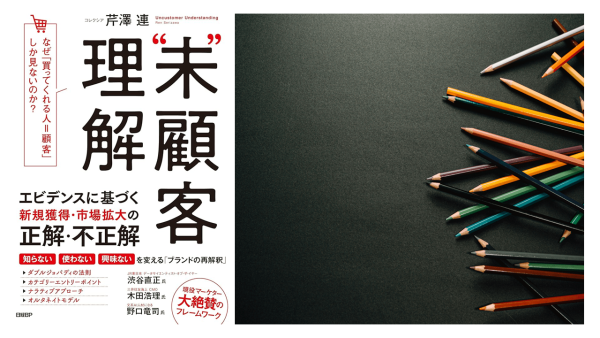私たちはなぜ、多くのブランドの中から特定のひとつを“思い出し”、選び取るのでしょうか?
その答えの核心にあるのが“想起集合”。つまり、あるカテゴリーで「選択肢」として頭に浮かぶブランド群です。
本記事では、想起集合の基本から、第一想起・純粋想起との違い、そしてカテゴリーエントリーポイント(CEP)を活用した“思い出される仕掛け”の設計法まで、ブランドが“選ばれる瞬間”を生み出すマーケティング実践論を徹底解説します。
想起集合(Evoked Set)とは?
想起集合(Evoked Set)は、消費者が特定の商品カテゴリーで「何かを買いたい」と思ったとき、頭の中に自然に思い浮かべるブランドや商品群を指します。
例えば「ビールが飲みたい」と思ったときに最初に思い出すブランド(例:アサヒ、キリン、サッポロなど)が、その人にとっての“想起集合”です。
マーケティングにおいて、この“想起集合”に入ることは極めて重要です。なぜなら、想起集合に入っていないブランドは消費者の選択肢にすら入らず、どれだけ広告や販促を展開しても、購入の検討テーブルにすら乗らない可能性が高いからです。
・想起集合は、通常2~3ブランド程度で構成されることが多い(カテゴリーや個人属性で変動あり)
・市場シェアの高いブランドの多くは「想起集合」に定着している
・商品の選択プロセスで、最初に“想起”されること自体が競争優位となる
と言えます。

想起集合と関連用語の違い・関係
ブランド戦略・調査実務では、想起集合(Evoked Set)だけでなく、以下のような関連概念もセットで押さえることが重要です。
第一想起(Top of Mind)
第一想起とは、想起集合の中でも“最初に思い出されるブランド”を意味します。
この“第一想起”を獲得するブランドは、消費者の頭の中に「そのカテゴリーと言えば=自社ブランド」というポジションを築いたことになり、最も高い購入確率を持ちます。
*第一想起は、一般的に市場シェアやブランド力と強く相関しており、広告・コミュニケーション設計のKPIとしても活用されます。
純粋想起(Unaided Recall)
純粋想起とは、「○○と言えば?」という自由回答型の調査質問で思い浮かべたブランドを集計するものです。
ブランドを一切提示せず、消費者の記憶だけで思い出してもらうため、“ブランド認知の深さ”を測る指標となります。
助成想起(Aided Recall)
助成想起とは、「この中で知っているブランドは?」という選択肢付き調査で認知されるブランドを集計するものです。ブランドリストを見せてチェックを入れてもらう形式なので、認知の裾野(広がり)や選択肢認知率を把握するのに向く。
考慮集合(Consideration Set)
考慮集合は、購入を“実際に検討する”段階でリストアップされるブランド群のことです。想起集合よりもさらに「買う気」に近いブランドのセットで、価格比較や特徴検討の俎上に載ります。
拒否集合(Rejection Set)
拒否集合とは、明確に“選ばない”と判断されたブランド群のことです。
「絶対に買わないブランドを教えてください」など“真剣に検討”する段階のブランド群の中から、「拒否集合」は選択肢から外すブランドを指します。
主要用語の違い比較表
| 用語 | 質問例 | 特徴・主な目的 | 購買検討への距離 |
|---|---|---|---|
| 第一想起 | 最初に思い出すブランドは? | No.1認知、購買確率最大 | もっとも近い |
| 想起集合 | 「○○といえば?」複数回答 | 選択肢に入るか | 近い |
| 純粋想起 | 「○○といえば?」自由回答 | 記憶の深さを測定 | 中間 |
| 助成想起 | 「知っているブランドは?」リスト選択 | 認知の裾野、広がり | やや遠い |
| 考慮集合 | 実際に検討するブランドを教えてください | 比較検討段階 | 想起集合より近い |
| 拒否集合 | 買わないブランドは? | 明確に除外 | 対象外 |
これらの違いを理解することで、「どの集合を強化すべきか?」「自社ブランドは今どこにいるのか?」を論理的に把握できます。
なぜ「想起集合」や「第一想起」が重要なのか?
「想起集合」や「第一想起」は、消費者の購買意思決定に最も強く影響する心理的な“選択肢”です。
1.第一想起ブランドの購買確率は圧倒的
消費者調査や市場分析では、「第一想起」=最初に思い出されるブランドが実際の購買シェアや選択率で他を大きく上回ることが繰り返し示されています。
例えばビールやコーヒーなどのカテゴリーでは、第一想起ブランドが市場シェアの50%以上を占めているケースも少なくありません。業界・カテゴリーにもよりますが、「第一想起ブランドが購買される確率は2位・3位の2~3倍」なというデータもあります。
2. 想起集合の“外”は、存在しないも同然
消費者の頭の中に想起集合として浮かばないブランドは、どれほど商品力や広告があっても「比較」「検討」「購入」の土俵にすら上がりません。
「知られている」だけでは弱く、「思い出される」ことが勝負の分かれ目となります。
3. 「ブランド認知→想起集合→第一想起」設計の重要性
ブランド認知は“知っている”ブランドを広げる入口
想起集合入りは“記憶に残り、選択肢として思い出される”状態
第一想起獲得は“圧倒的No.1記憶”であり、ブランドの“勝ちパターン”の象徴
だと言えます。
この一連の流れをマーケティング戦略として意図的に設計し、「どうすれば想起集合・第一想起に入れるのか」=“思い出す瞬間”をいかに創出するかが、競争優位性を高める本質的なポイントです。
「思い出す文脈(CEP)」や「購入シーン」も分析しながら、“消費者の頭の中のポジション”獲得を目指すべきということです。
カテゴリーエントリーポイント(CEP)との繋がり
カテゴリーエントリーポイント(CEP)とは、消費者が特定の商品カテゴリーを“思い出す”きっかけとなる「状況」「タイミング」「ニーズ」や「使うシーン」を指します。
例えば、「暑い日に喉が渇いた」と感じたときに「ビール」というカテゴリーが頭に浮かぶ――これが典型的なCEPです。
CEPを戦略的に設計・活用することで、「暑い日に飲みたい」→「ビール」→「○○ビール」と、自社ブランドが“選ばれるストーリー”の起点を作り出すことができます。
つまり、“どんな文脈で自社が思い浮かぶか”を設計することが、そのまま“想起集合の入口”を増やすことにつながるのです。
実際、想起集合に入りやすいブランドは、カテゴリー内の様々なCEPを複数獲得している(=“想起される状況”が多いほど想起集合シェアが拡大)と言えます。
CEP活用の実務ポイント
①生活者の“思い出すシーン”を徹底リストアップする
例:「仕事帰りの一杯」「友人と宅飲み」「真夏のBBQ」など、あらゆるCEPを想定し、ブランド訴求を掛け合わせる。インタビューやSNS、検索ワード分析で“本当に思い出される瞬間”を特定する
②CEPに紐づいたコミュニケーション設計
CM・デジタル広告・店頭体験などで、「特定シーンで思い出される」演出やコピーを繰り返し刷り込む。
例:「◯◯のときは、やっぱり○○ビール!」などの“文脈特化型”訴求
③CEPの強化による想起集合への“入り口”づくり
消費者が思い出す“場面”や“セリフ”を、ブランドと一体化させることで、想起集合・第一想起の確率を上げる。
「○○シーンと言えばこのブランド」という記憶設計が競争力になる。
このように、CEPを意識したマーケティング設計は、単なる認知拡大ではなく「思い出される状況」そのものを創る戦略です。
“想起集合”はブランドコミュニケーション・市場ポジション設計の出発点。
そして「どのような状況で自社ブランドが消費者の頭に浮かぶのか?」という“文脈の設計”が、第一想起や考慮集合への強い導線となります。
まとめ
このように、“想起集合”に入るかどうかが、ブランドが「選ばれるか否か」を大きく左右します。
単なる認知の獲得ではなく、「どんなシーンで、どんなタイミングで消費者の頭に浮かぶか」を戦略的に設計することが、競争優位をつくるマーケティングの本質です。
今こそ、CEP(カテゴリーエントリーポイント)を軸に、想起集合・第一想起を狙うアプローチを自社ブランド戦略に取り入れてみてください。
リスニングマインドは、検索データを網羅的に分析し、隠れた消費者インサイトを可視化することで、ブランドが取るべき戦略の方向性を明確にします。
ぜひ、検索データからカテゴリーエントリーポイントや想起集合に入るための記憶設計のヒントを見つけてみてください。
【おすすめの記事】
・消費者インテントから探るカテゴリーエントリーポイント(CEP)
・[レポート]検索データから見つける新たなCEPの兆し:プロテイン