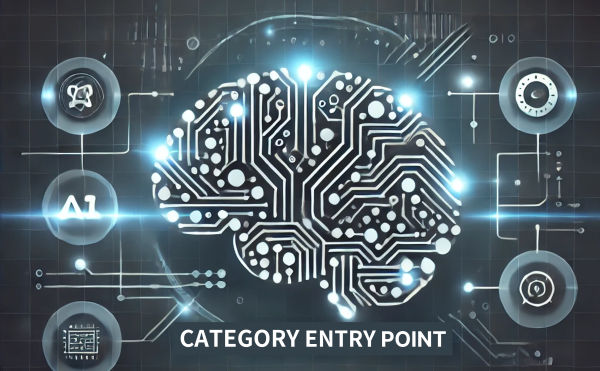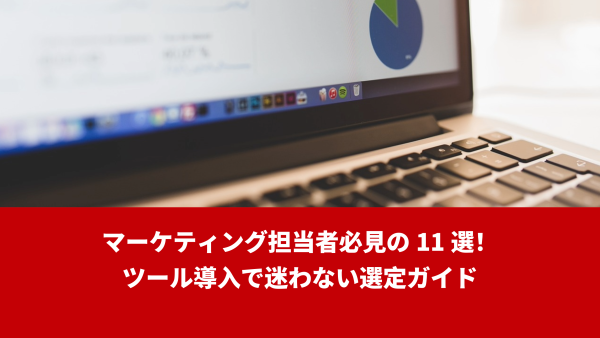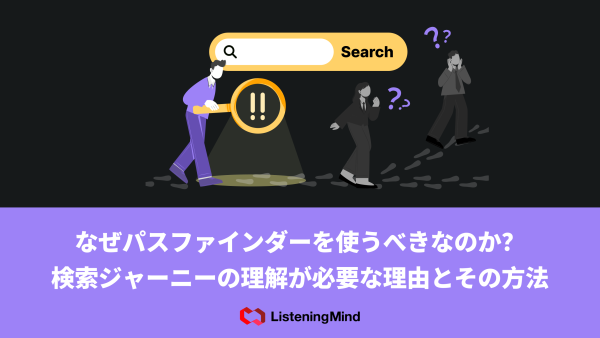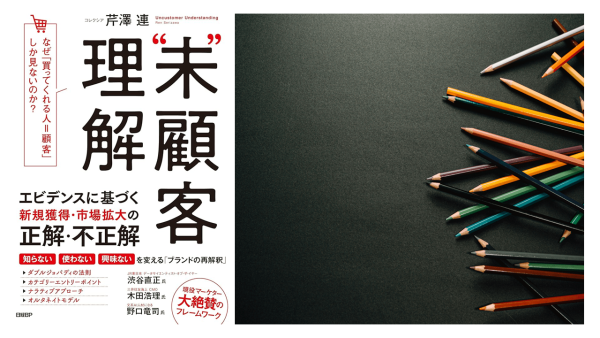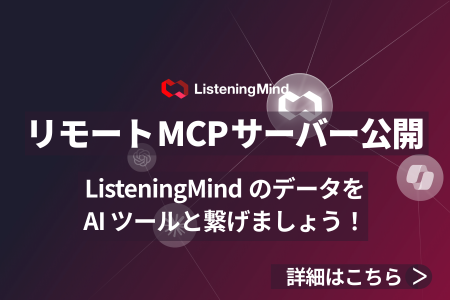カスタマージャーニーマップを作成したにも関わらず、施策に繋がらない・マップが仮説に偏ってしまったという経験はありませんか?従来のカスタマージャーニーマップ(CJM)は、インタビューや経験則に基づきがちで、「顧客のリアルな行動」や「具体的な検索ニーズ」を反映しきれないという課題がありました。
本記事では、カスタマージャーニーの概念から作り方、顧客の“リアルな行動”を反映した検索データを活用し、より精度の高いカスタマージャーニーマップを作成・活用する具体的な方法を解説します。
1. カスタマージャーニーとは?基本概念とマーケティングでの役割
1-1. カスタマージャーニーの定義と重要性
カスタマージャーニー(Customer Journey)とは、消費者が「何かが欲しい」「課題を解決したい」と思い立った瞬間から、関連情報を集め、商品やサービスを比較・検討し、最終的に購入や契約に至るまでの一連の行動・心理の変化を可視化したフレームワークです。
このプロセスには、検索、広告接触、SNS、口コミ、レビュー、実店舗での体験など、非常に多様な接点が存在します。そしてこの一連の流れは、一人ひとりの行動でありながらも、類似したニーズを持つ消費者が多く存在することで、市場全体の構造的動向をも映し出しています。
たとえば、「子ども用の自転車を探している母親」「転職を考える20代」「肌荒れに悩む男性」など、それぞれ異なる文脈を持った人々が、ある共通の目的に向かって同じように行動しています。その購入までの過程を可視化・体系化するのがカスタマージャーニーという考え方です。
1-2. カスタマージャーニーの主な5つの段階(フェーズ)
カスタマージャーニーは一般的に、顧客が課題に気づき、情報を集め、比較し、購入し、利用へ至るまでの流れを次の5つのフェーズに分けて整理します。
- 認知(Awareness): 課題に気づいたり、情報収集を始める初期段階。悩みの原因を調べる、キーワードで検索する等。
- 興味・関心(Interest): 課題の解決方法や商品カテゴリに興味を持ち、選択肢を広げる段階。特定のブランドや商品について調べ始める等。
- 比較・検討(Consideration): 複数の商品・サービスを比較し、自分に最適な選択肢を探す段階。
- 購入(Purchase): 価格、口コミ、機能を最終確認し、意思決定を行う段階。
- 利用・継続・推奨(Retention / Loyalty): 実際の利用体験から満足度が形成され、リピートや友人への推奨につながる段階。
2. カスタマージャーニーマップ作成のメリットと活用戦略
2-1. カスタマージャーニーマップ(CJM)とは
このジャーニーを視覚的に整理し、フェーズごとにどのような行動や感情、接点があるのかをまとめたものがカスタマージャーニーマップ(CJM)です。
カスタマージャーニーマップは、マーケティング戦略立案の出発点として非常に有効です。広告のタイミング、Webコンテンツの配置、チャネルの最適化、カスタマーサポートの配置など、あらゆる施策の優先順位と目的を明確にする土台となります。
2-2. カスタマージャーニーマップのメリット
カスタマージャーニーマップを作成し活用することで、マーケティング活動全体にわたり、次のようなメリットがもたらされます。
- 顧客理解を正確に可視化できる:
顧客が「いつ・どこで・何を考え、どう行動するのか」を可視化することで、社内の思い込みや“作り手目線”を排除し、顧客視点に立った判断ができるようになります。 - ボトルネックを特定し、改善の優先順位をつけられる:
離脱ポイントや不満が生まれやすいフェーズを特定できます。改善すべき箇所が明確になるため、限られたリソースでも効果的な打ち手を選択できます。 - 部門間で共通認識が生まれ、組織横断の連携が進む:
マーケティング・営業・CS・開発などが、同じジャーニーをベースに議論できます。“顧客中心”という共通言語ができ、部署間の認識のズレやムダ施策を減らせます。 - コンテンツマーケティングの質と優先順位が明確になる:
フェーズごとに顧客が求める情報が見えるため、必要なコンテンツが明確になります。何を、いつ、どの順番で作るべきかを判断しやすく、オーガニック流入獲得に役立ちます。
3. カスタマージャーニーマップを手動で作成する5つのステップ
まずは、一般的なカスタマージャーニーマップ作成の5つのステップを解説します。
ステップ1:ペルソナ(ターゲット像)の設定
ジャーニーの主人公となる具体的な顧客像(年齢、職業、目標、課題など)を設定します。このペルソナが抱える悩みと目標が、マップ作成の起点となります。
ステップ2:ジャーニーの範囲とフェーズ(段階)の定義
認知から利用・継続までの段階を定義し、各フェーズでペルソナが「どのような行動」を取るのかを洗い出します。
ステップ3:行動・思考・感情・タッチポイントの洗い出し
各行動の裏にある顧客の思考(何を考えているか)、感情(ポジティブかネガティブか)、タッチポイント(どこで接点を持つか)といったインサイトを具体的に特定します。この際、インタビューやアンケートなどの定性調査が中心となります。
ステップ4:課題と機会(ボトルネックと改善点)の特定
感情がネガティブになる部分(離脱や不満の原因となるボトルネック)を明確にし、そこから生まれる提供すべき価値や情報(改善の機会)を導き出します。
ステップ5:マップの完成と施策への落とし込み
洗い出した要素を一覧化し、誰が・いつ・何を改善するかを明確な施策として落とし込みます。
4. 従来のマップ作成が抱える課題と検索データの必要性
4.1 従来のカスタマージャーニーマップの課題
上記の5ステップでマップは作成できますが、特にステップ3の“行動・思考・感情の洗い出し”において、従来のカスタマージャーニーマップは以下が課題として挙げられていました。
- 課題1: データ裏付けの不足と仮説依存
インタビューや担当者の経験といった定性的な情報や仮説に依存しやすく、マップ上の行動や思考が客観的なファクトに乏しくなりがちです。 - 課題2: 施策への落とし込みの難しさ
作成したマップから、具体的な施策、特にコンテンツ制作に必要なキーワードやリアルタイムのニーズが導き出しにくい。
一方で、顧客が検索エンジンに入力するキーワードは、“その瞬間の疑問・興味・課題”を直接示す最もリアルな行動データです。この検索データを活用することで、従来のジャーニーマップを仮説中心のモデル”から“実行可能な設計図”へアップデートすることが可能になります。
4.2 検索データが示すインテント(意図)の可視化
現代の消費者は、何かを知りたい、比べたい、決めたいと思った瞬間に、スマートフォンで検索を行います。これは日常の中で自然に起こる行動であり、その行動には明確な意図(インテント)が潜んでいます。

例えば、
- 「電動自転車 子ども 2人乗り」→ 安全性や耐荷重が気になる親
- 「30代男性 化粧水 敏感肌」→ 肌荒れに悩み、適切な製品を探す人
- 「引っ越し いつ安い」→ タイミングとコストに悩む生活者
こうした検索ワードには、消費者の具体的な“今の困りごと”や“判断基準”が凝縮されています。企業やマーケターにとって、これらはまさに無言のアンケートともいえるデータです。
検索データをもとにしたインサイトは、以下のように消費者の購買段階や気持ちを詳細に把握するために活用できます。
- 初期探索段階か、購入直前かの把握
例:「◯◯とは」や「◯◯ おすすめ」は初期段階、「口コミ」「クーポン」は購入直前のステージに多く出現。 - 重視ポイントの抽出
例:「コスパ」「静音」「軽量」などのワードが含まれていれば、その商品の選定基準が把握できます。 - 不安や不満の可視化
例:「◯◯ 壊れやすい」「◯◯ トラブル」といったワードは、購入に対する“心理的障壁”の存在を示しています。
このように検索ワードからは、消費者の行動だけでなく、思考の変化や心の動きまで読み解ける重要な手がかりとなります。
4-3. 検索インテント分析で実現する7つの具体的な可視化

- ① 購買要因の抽出
「7人乗り SUV」や「小型 EV 200万円以下」などの検索は、広さや価格を重視していることが分かります。検索ワードと検索数から、購買の際にどの要素が意思決定に影響を与えているかを定量的に把握できます。 - ② 関心トピックの特定と優先順位付け
「肌に優しい日焼け止め」の検索数が増加していれば、敏感肌や成分に関心が集まっていると言えます。どのトピックに対して検索数が多いかを段階別に分析することで、ユーザーの関心度合いや関心の変化、トレンドの兆しを読み取ることができます。 - ③ 非補助認知度(Top of Mind)測定
自ら思い浮かべて検索したブランドが、その人の“第一想起ブランド(Top of Mind)”です。ブランド名を指名検索する人の数は、広告では測れない自然な認知の強さの指標となります。 - ④ 競合比較と検索シェア分析
「A社 B社 どっち」のような比較検索は、ユーザーがすでに購入候補を絞っていることを示します。このタイミングでの検索は、購入直前の“最後の一押し”に影響を与える重要なデータです。 - ⑤ 不満・課題の早期検知
「冷蔵庫 うるさい」「エアコン 水漏れ」などのネガティブキーワードは、ユーザーが既に製品を使っている状況で抱えている不満を示します。これらを拾い上げることで、商品改良やカスタマーサポート改善につなげられます。 - ⑥ 影響チャネルの特定
検索結果画面に上位表示されるWebメディア、比較サイト、YouTube動画などは、ユーザーの意思決定に大きな影響を与えます。企業の公式サイト以外で誰が発信しているのかを把握することも重要です。 - ⑦ 市場セグメント別の関心度・規模推定
例えば「学習机 中学生」「学習机 幼児」のように利用対象が明確に異なる場合、それぞれのセグメントにおける関心度や市場規模を検索データから相対的に見積もることができます。
ジャーニーファインダーによる革新的なマップ作成
上記で解説したように、従来のカスタマージャーニーマップは、ステップ3(行動・思考の洗い出し)とステップ4(ボトルネックの特定)に、多くの時間とリソースを消費する上にデータ不足に陥りやすい部分でした。自社の顧客ではない潜在顧客(未顧客)がどのような課題を持ち、どのような言葉で情報を探索しているかを、企業が保有しているデータだけで把握することは困難です。
この課題を解決するために、検索データとAIキーワード分析を組み合わせたジャーニーファインダー機能が開発されました。
ジャーニーファインダーとは?カスタマージャーニーを自動作成するAIツール

ジャーニーファインダーは、カスタマージャーニーマップを作りたいけどどんなデータを使えばいいのか分からない、検索ワードを分類するにも時間がかかるという長年の悩みを解消する、カスタマージャーニー自動作成ツールです。
キーワードを入力するだけで、関連検索語を瞬時に収集・分類し、顧客がどのように情報を探索し、購入を決定するかを段階的かつ定量的に示します。これにより、以下のことが一目で理解できます。
- 各フェーズで顧客が何を気にしているのか
- どんな代替案を比較しているのか
- 何を最も重視しているのか
競合優位性を把握するドメイン表示機能

さらに、ジャーニーファインダーのドメイン表示フィルターを使うことで、各フェーズにおける自社と競合の検索上位シェア状況を視覚的に確認できます。顧客の検索行動において、競合他社や自社がどの段階でどれだけ露出されているか(検索結果の上位にいるか)を把握できるということです。
この機能により、カスタマージャーニーマップを基にした競合分析を行い、ブランドのポジショニングやコンテンツ戦略の最適化を図ることが可能になります。
ジャーニーファインダーで実現できること
ジャーニーファインダーは、貴社のマーケティング活動に以下の価値を提供します。
- 顧客の検索意図をAIで分析し、購買行動の全体像を把握
- ブランド認知から購入・利用後までの体験をデータで理解
- コンテンツ戦略・マーケティング施策の精度を向上
- 競合分析を通じてブランドのポジショニングを最適化
まとめ:検索データ活用でLTV向上へ
カスタマージャーニーマップは、作成すること自体が目的ではありません。顧客の行動と感情を深く理解し、一貫したCX(顧客体験)を提供し続けることで、売上拡大とLTV(顧客生涯価値)向上に寄与します。
検索データは、単なる「調べものの記録」ではありません。それは、生活者の意図と感情、悩みと期待、選択の理由が詰まった“未来のヒント”そのものです。
企業がこのデータを通して本当のニーズに耳を傾け、ジャーニーの各段階で適切なコンテンツや体験を届けることができれば、広告費の最適化やCV向上を超えた、ブランドへの共感やファン化につなげることが可能になります。
そして何より、マーケティングとは伝えることではなく、聴くことから始まるべき時代に突入しています。検索という“声なき声”を丁寧に読み解くことこそが、これからのマーケティングの本質であり、競争優位を築く最大の鍵となるのです。
検索データを活用したカスタマージャーニーマップの作成、ジャニーファインダーが気になる方はお気軽にお問合せください。