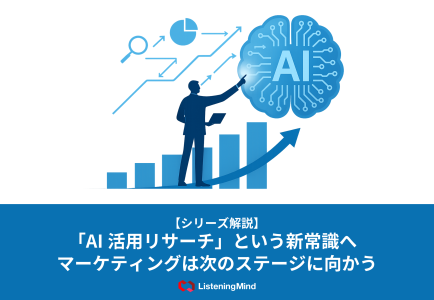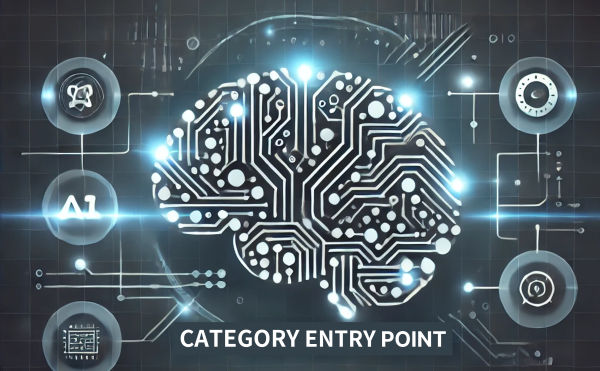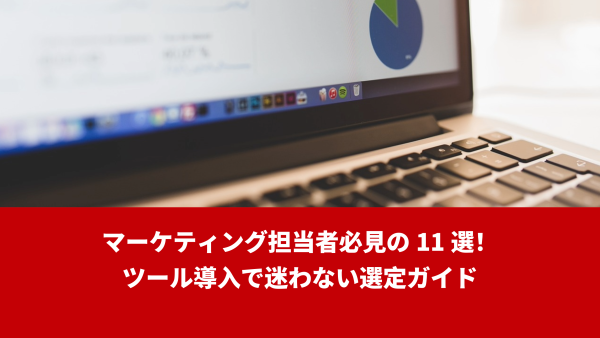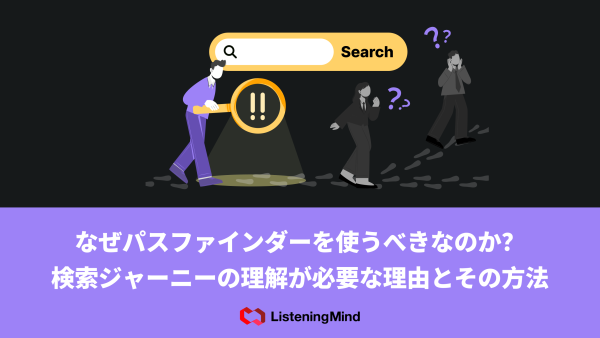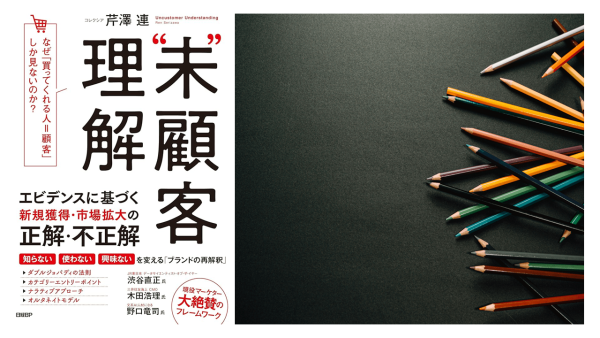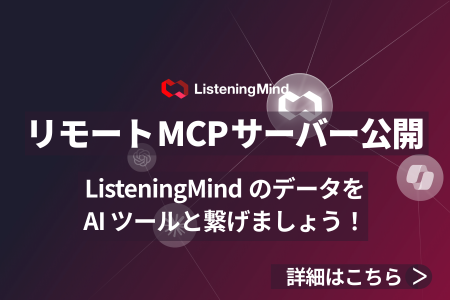生成AIの登場は、マーケティング、リサーチ活動の世界に大きな可能性をもたらしました。その一方で、「もっともらしい間違い(ハルシネーション)に振り回された」「結局、どう実務に活かせばいいのかわからない」――。私たちのもとには、そんな切実なご相談が数多く寄せられます。
私たちアセントネットワークスは、デジタル・マーケティング分野のテクノロジー・リード・カンパニーとして、こうした課題と日々向き合い続けています。その中で見えてきたのは、目先のテクニックを追うのではなく、分析、リサーチの「あり方」そのものを捉え直す視点こそが必要だということです。
では、これからの時代に求められる、分析・リサーチの新しい「あり方」とはどのようなものでしょうか。 私たちは、実践的な「AI活用リサーチ」を実現するためには、次の4つの必須要件が不可欠だと考えています。
- ハルシネーション・レス: 信頼できるデータ基盤を用意して分析を行うこと。
- パーセプション・ギャップの解消: 「思い込み」の壁を壊して調査を進めることができること。
- オンデマンドな表現手段: 思考のスピードを落とさずアウトプットできること。
- 従来は不可能だったことの克服: 単なる「効率化」に留まらず、分析の「成果」そのものが向上できること。
本シリーズでは、この4つの要件を一つずつ、それぞれ1回の記事として詳しく解説していきます。本記事では以下に、各回のテーマと概要をご紹介していきます。
第一回 ハルシネーション・レス(Hallucination-less)

~信頼できるデータ基盤で調査を行える準備が必須に~
シリーズ第1回は、すべての分析の土台となる要件”ハルシネーション・レス”をテーマにします。
生成AIが時に誤りを犯すのは、テキスト生成モデルとしての宿命とも言えます。しかし、だからこそビジネスという重要な意思決定で用いるには、AIを具体的なデータ基盤へ接続し、「AI内部の知識」と「外部の事実」とを意識的に使い分けるプロセスが欠かせません。それこそが、分析の土台となる情報の「正しさ」を担保する、第一の、そして最も重要な要件です。
このレポートでは、こうしたデータ基盤の有無が分析にどれほどの違いをもたらすか、比較実験をお見せします。同じプロンプトで「洗濯用洗剤」の市場分析を指示した時、「AIの知識体系に基づいた分析」と「消費者分析データ基盤に接続したAIの分析」のアウトプットは、大きく異なる様相を呈します。一方は“世間のイメージの再生産”、もう一方は“消費者の多様な視点”。さらに、この2つのレポートを、背景を知らない第三のAIに「どちらが優れているか」評価させます。そして最後に、データ基盤の有無を明らかにした時、AIの評価はどう覆るのでしょうか。分析を評価するAIの分析を通じて、AIと人間の協業とはどのような形であるべきなのかを解説します。
第二回 パーセプション・ギャップの解消(Perception Gap)

~どこから、どのように調査するか、という躓(つまづ)きをAIで乗り越える~
調査の切り口にバイアスがあったり、固定化してしまったりして、分析が行き詰まる。これは、誰しもが陥りがちな課題ではないでしょうか。これに対し、生成AIはいわば無数の“視点の引き出し”を持っています。信頼できるデータ基盤と連携させることで、AIはデータ全体を多角的に俯瞰し、消費者の実態を捉えるための多様な視点を提案することが可能です。このアプローチでパーセプション・ギャップを乗り越えることは、今後のマーケティング分析を担当するうえで必須のスキルとなるでしょう。
しかし、問題はそれだけではありません。消費者自身も、無意識に本音とは違うことを言ってしまうものです。これが、調査される側の“無意識の壁”です。このギャップを打ち破る鍵として、このレポートでは消費者の「意図・動機」を明らかにする手法として『インテントマーケティング』を取り上げます。この中では、検索データ、SNSデータ、パネルデータといった各情報ソースの特性の違いにも触れながら、インテントマーケティングを用いて「消費者自身も気づいていない」パーセプション・ギャップを克服する方法を解説します。調査する側とされる側、その双方に存在するこの根深い課題をいかに解消するか。このことは現代のマーケティングテクノロジーが取り組む最重要テーマの一つです。
第三回 オンデマンドな表現手段(On-demand)

~分析だけでなく、データ整形も自動化する~
分析の方向性が見えても、そこからレポート用にデータを深掘りしたり、グラフを作成したりといった作業は、依然として手作業であることがほとんどです。どんなに優れた洞察も、伝わる形にアウトプットできなければ価値を生みません。だからこそ、これからのリサーチ業務には、定型的なダッシュボードに縛られることなく、分析からアウトプットまでを柔軟かつ即座にカスタマイズできる環境が必要です。本レポートではAIを活用して、こうしたプロセスを実現するための最新の手法についてご紹介します。
また本レポートでは、こうした変化が、 単なる省力化ではなく、現在の生成AIが起こしている本質そのもの、”man-machine interface”の変化であるということについても解説します。今後、私たちがこれまで慣れ親しんできた、無数のアプリやウェブサイトが持つ独自の操作画面(UI)は、次第に生成AIへと置き換わっていくでしょう。その時、様々なサービスの価値は、使いやすいUIから、その背後にある「信頼できる独自のデータ基盤」や「優れた分析エンジン」そのものへと移行します。こうした未来像をいち早く体験できる実例として、「リスニングマインド」とChatGPTの協働による分析プロセスを例にご紹介します。
第四回 従来は不可能だったことの克服(Beyond)

~これまでの作業の効率化ではなく、これまでの成果を超える~
生成AIの価値は、単なる「効率化」ではありません。その本当の目的は、これまで困難だった壁を乗り越え、アウトプットの“質”そのものを飛躍させることです。この「質的変化」は、決して大げさな話ではなく、普段の業務の中にこそ現れます。このレポートでは、その例として「レーダーチャート分析」を取り上げます。たとえ大規模なデータを購入し、精緻に前処理しても、凡庸な結果にしかならない、そのような事はよくあります。なぜなら、分析の成否を分けるのはデータ処理の精度以上に「評価軸の設定」だからです。
しかし、調査目的に適い、かつデータから本質的な価値を引き出す評価軸を設定することは、これまで非常に困難でした。この課題に対し、AIを活用することは大きな進歩をもたらします。AIはデータそのものを解釈し、多様な視点から有効な評価軸を何パターンも提案できます。本レポートではこうした評価軸の策定に関する例をいくつかご紹介します。こうしたことに派手さはありませんが、実務者であれば、それが画期的であることが分かるトピックであると思います。
これらは決して個別のテクニックではありません。この4つのテーマそれぞれを具体的に実現することで、初めて生成AIはビジネスに役立つパートナーとなります。この変化の激しい時代において、AIを単なる効率化ツールとして捉えるか、自らの能力を拡張するパートナーとして捉えるかで、未来は大きく分岐します。
本シリーズが、その分岐点で迷うすべてのマーケター、アナリスト、そしてビジネスパーソンにとって、確かな羅針盤となることを確信しています。
この記事のタグ