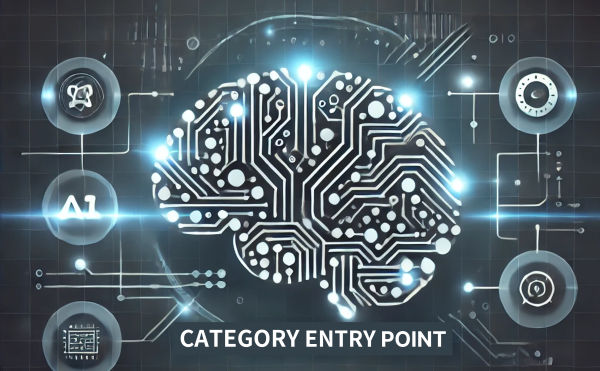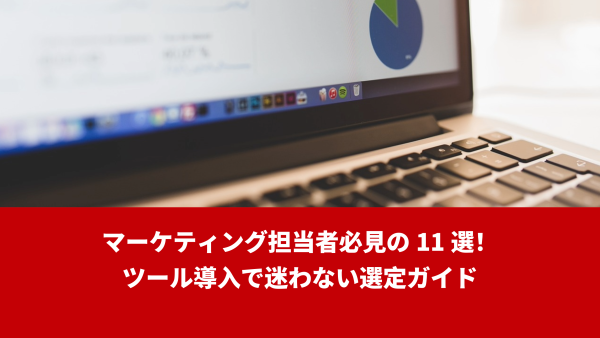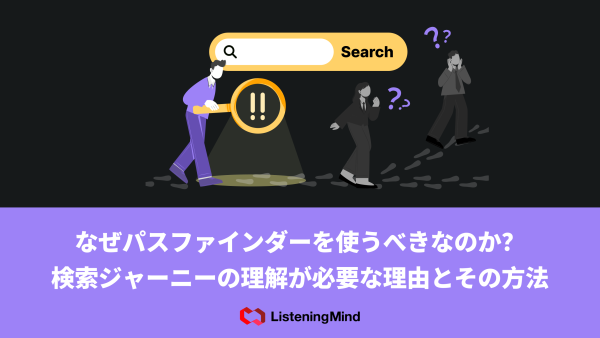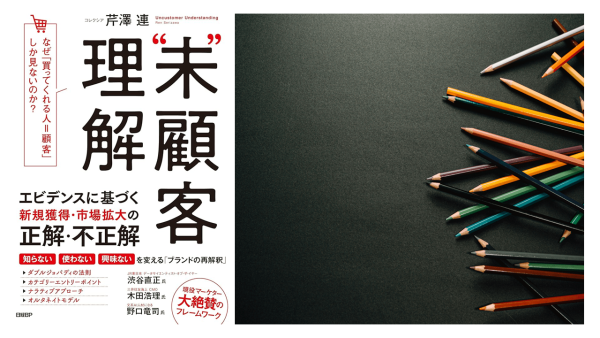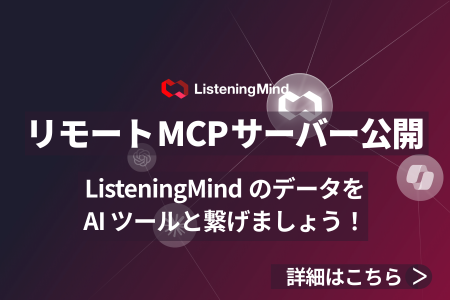はじめに:AIの過渡期ゆえの見通しづらさが目立った
AIマーケティングとは?
AIマーケティングとは、人工知能を活用して、消費者理解・意思決定・ブランド体験の最適化を図る手法を指します。現在のマーケティング業界は、AI技術の発展による激しい変化のただ中にあります。カンファレンスでは、「AIをテーマにせざるを得ない登壇者」と「AIの効果を実感できない参加者」が交錯し、まさに混沌ともいえる状況が見られました。
「AIを導入すること」が目的化し、本来問われるべき「AIをどう活用すべきか」という視点が欠落している点が印象的でした。この混乱は技術の未成熟さだけでなく、AIの本質に対する理解不足からも生じています。
多くの議論が「AIで何ができるか」に終始する中で、「AIをどう活かすか」という問いこそが、いま最も重要であると言えるでしょう。
第1章:生成AIを理解しよう
生成AIとは?
生成AIは、人間の自然言語を通じて複雑なシステムと対話し、意図を実行可能な形に変換して返す「インターフェース」です。単なる出力(コンテンツ生成)そのものが目的ではなく、外部システムと連携して価値ある行動や情報提供を仲介する役割が本質です。
1-1. 「なんでも生成器」ではなく、「インターフェース」
生成機能への過度な期待
近年、生成AIに関する議論の多くは、その“生成能力”そのものに注目しています。確かにAIがもたらすコンテンツ生成やパーソナライズ、製品開発の可能性は目を見張るものがあります。しかし、これはAIの本質の一部にすぎません。
UnileverのCMOが述べたように、「AIはコンテンツを大量生産するためのものではなく、ブランドを築くための“大きな創造的思考”を支える存在」であるべきです。
IKEAの“爆発する箱”エフェクトが象徴するように、AIで簡単に作れるものほど「似たようなものの海(a sea of sameness)」に沈んでいく危険があります。
生成AIの本来の役割は、「インターフェース」
従来、人間がコンピュータと対話するためには、特定の操作手順やコマンドを覚える必要がありました。しかし生成AIは、自然言語という人間にとって最も自然な方法で、複雑なシステムと対話することを可能にします。

つまり、生成AIは:
- 人間の意図を理解する
- 適切な外部システムに接続する
- 結果を人間が理解できる形で返す
という「通訳」「仲介者」としての役割こそが本質であると考えられます。
まだまだ過渡期にある、接続性
この観点から言えば、 単体の生成AIではなく、生成AIとどのような外部連携(MCP, RAG)エコシステムを構築するか、が重要になります。
重要なのは「クリエイティブ機能」よりも「インターフェース」であり、その先にある接続されたエコシステム全体と言えるでしょう。(そして、真に革新的なインターフェースは、まだ登場していないのが現状です)
1-2. インターフェースの完成:RAGとMCPが接続される環境
RAG(Retrieval-Augmented Generation)とは?

RAGは、LLMが持つ知識の限界を補完する技術です。
LLMは学習時点の情報で「凍結」されているため、リアルタイム情報や企業固有の情報にアクセスできません。RAGは、質問に応じて外部データベースから関連情報を検索・取得し、それをもとに回答を生成することで、この問題を解決します。
例えば:
- 企業の内部ドキュメント
- リアルタイムの価格情報
- ユーザーの購買履歴
これらにアクセスすることで、 LLM単体が生成する一般的な製品リストよりも、コマースデータで強化された専用システム(ハイブリッドアーキテクチャ)からの推奨の方が、はるかにユーザーの関心を引くことができると考えられます。
MCP(Model Context Protocol)とは?

MCPは、AIが外部のツールやサービスと連携するためのプロトコルです。
単に情報を取得するだけでなく、実際に「アクション」を実行する能力を付与します。例えば:
- 特殊な機能
- 外部のデータ基盤
これにより、AIは「情報提供者」から「実行者」へと進化します。
第2章:消費者側に起こる変化
2-1. エージェンティック・コマースの台頭
現在、「Agentic Commerce」という言葉は、2つの全く異なる意味で使われており、混乱の原因となっているようです:
❶事業者視点のAI:AI sales agents = ChatBot

自社サイト内で接客・販売を行う「営業マン」のような役割です。技術的ハードルが低く、コールセンター費用削減などの観点から最も取り組まれてきた既知の分野と言えます。
❷消費者視点のAI:エージェンティック・コマース

複数サイトを横断し、利用者の利益を最大化する「代理人」のような役割です。プライバシー(ローカル志向)やUXのパーソナライズ(アクセシビリティの個別化)という重要な課題へ包括的に取り組むものとなります。
❷の発展が目指されている中で、❶の成長は限定的 になる可能性が考えられます。その背景として、❷が目指すものは、単なる購買行動の効率化だけでなく、より本質的な消費者の権利と体験の向上を目指しているからだと考えられます。
購買プロセスの劇的な変化
消費者が自分専用のAIエージェントを持つようになると、購買行動は劇的に変化すると予測されます。
従来の購買プロセス
- 企業の広告やマーケティングメッセージに接触
- 検索エンジンで情報収集
- 複数のサイトを比較検討
- 購入決定
このプロセスでは、 企業側が情報の提示方法によって消費者をコントロールすることが可能でした。
エージェンティック・コマース時代
- 消費者がAIエージェントに要望を伝える
- AIエージェントが複数サイトを自動的に横断検索
- 消費者の過去の行動、嗜好、予算などを考慮して最適化
- 推奨案を提示(または自動購入)
このプロセスでは、 情報の取得と評価をAIエージェントが代行するため、企業側のコントロールは大幅に減少すると考えられます。
2-2. GEO(Generative Engine Optimization)の実際
GEOとは?
GEOは、生成AIが結果を要約・提示する際に自社を“引用される情報源”として最適化する手法です。構造化データ、信頼性の高い情報、更新性が鍵となります。
従来のSEOは、検索エンジンの結果ページに自社サイトを上位表示させることが目的でした。
しかし、 生成AIが検索結果を要約して提示する時代 においては、新たな最適化が必要となると考えられます。それがGEO(Generative Engine Optimization)です。
GEOの実際

最新の調査(ヴァリューズ×note共同調査)によると:
- Googleなど検索エンジン自体の検索ユーザー数は減っていない状況です
- 従来の検索流入とは別に、「生成AI経由のトラフィック」が新しい集客経路として立ち上がりつつあります
- 生成AIの要約によって来訪が減る記事と、以前より来訪者が増える記事の2極化 が示唆されています
つまり、AIが検索結果を表示する際に、 信頼できる情報源として自社サイトが「引用」され、ユーザーがクリックして詳細を確認できるようにサイトを構築する必要があります。
GEO対策の方向性
- 構造化された高品質なコンテンツ
- 信頼性の高い情報源としての評価
- AIが引用しやすい形式での情報提供
- リアルタイムで更新される正確な情報
これは単なるテクニカルな対策ではなく、 ブランドが信頼される情報源であり続けるための本質的な取り組み と言えるでしょう。
2-3. 発信者コントロールの終焉
消費者自身がAIを活用して購買するようになると、受け取り側がコントロールするので、発信者側がコントロールする手法は限界を迎える可能性があります。
この変化は、マーケティングの本質を根本から問い直すものとなります。
パラダイムシフト
●従来のマーケティング は:
- いかに目立つか(アテンション)
- いかに説得するか(パースエイション)
- いかに記憶に残るか(リコール)
という プッシュ型の発想 でした。
●AIエージェント時代のマーケティング は:
- いかに発見されるか(ディスカバラビリティ)
- いかに信頼されるか(トラスト)
- いかに選ばれるか(プリファレンス)
という プル型の発想 へと転換していきます。
第3章:信頼の構造を理解する
システム信頼とは?──個人か、システムか
システム信頼とは、個々の影響力のある人物ではなく、プラットフォームやレビューシステム、アルゴリズムやコミュニティといった“仕組み”そのものに対する信頼を指します。これが確立されることで消費者の自信が高まり、購買行動に良い影響を与えます。
3-1. 重要なキーワード群:帰属意識、信頼、意欲、自信
カンファレンス全体を通じて、以下のキーワードが繰り返し登場しました:
❶帰属意識 (Belonging)
❷信頼 (Trust)
❸意欲 (Motivation)
❹自信 (Confidence)
これらは一見バラバラな概念に見えるかもしれませんが、実は 消費者の購買意思決定プロセスにおける心理的基盤 として、密接に関連しています。
3-2. 自信の欠如とシステム信頼
Pinterestのセッションで語られた「 FOBO(Fear of Better Options) 」—「もっと良い選択肢があるかもしれない」という恐れ—は、現代の消費者が抱える根本的な問題を象徴していると言えます。
オンラインショッピングカートの70%が放棄される(カゴ落ち)という現象は、単に価格比較や配送料の問題だけではありません。 「これで本当に良いのか」という自信の欠如が根本原因であると考えられます。
そして、 この自信の欠如は、消費者のシステム信頼の欠如と読み替えることができるのではないでしょうか。
3-3. 信頼の対象:個人か、システムか
現代マーケティングでは、レビューやインフルエンサーの重要性が強調され、 個人への信頼 にフォーカスが当たることが多いようです。
確かに:
- 「この人が勧めているから信頼できる」
- 「このレビュアーは信頼できる」
- 「このインフルエンサーのセンスが好き」
という個人ベースの信頼は、現代の購買行動において重要な役割を果たしています。しかし、 これもシステム信頼の現れ方の一つである と捉えることができます。
3-4. システム信頼という概念
重要な問いは、「特定のYouTuberを信頼するのか、YouTuberだから信頼するのか」という点です。もし後者であれば、それは個人への信頼ではなく、「YouTuberというシステム」への信頼と言えます。同様に:
- 「レビューシステム」への信頼 :個々のレビュアーではなく、集合知としてのレビューシステムを信頼している
- 「プラットフォーム」への信頼 :Amazon、楽天、YouTubeといったプラットフォームそのものへの信頼
- 「アルゴリズム」への信頼 :推奨システムが自分に合ったものを見つけてくれるという信頼
- 「コミュニティ」への信頼 :特定のコミュニティに属する人々の判断への信頼
花王のヘアケアマーケティングの事例で見られたのは、まさにこの システム信頼の構築 と言えるでしょう。「美容オタク」というコミュニティが持つ帰属意識を活用し、そのコミュニティへの信頼を通じて、商品への信頼を獲得しています。
3-5. 信頼から意欲と自信へ:好循環の創出
システム信頼が構築されると、以下の好循環が生まれます:
- 帰属意識 が生まれる:「このコミュニティに属している」という感覚
- 信頼 が醸成される:「このシステム/コミュニティは信頼できる」という確信
- 意欲 が湧く:「このシステムが推奨するものを試してみたい」という動機
- 自信 が生まれる:「この選択は正しい」という確信
このサイクルが回ることで、 カゴ落ちは減少し、購買は促進されると考えられます。
逆に言えば、個別の製品やブランドへのマーケティング施策だけでは不十分である可能性があり、消費者が安心して意思決定できる「システム」を提供することが、企業の重要な役割となると言えるでしょう。
第4章:事業者側に起こる変化
4-1. ペルソナから行動分類へ
行動分類とは?
属性に基づくペルソナではなく、実際の行動データ(購買履歴、サイト内行動、検索クエリなど)を基に「今のニーズや意図」を把握する手法です。AI活用によりリアルタイムでの状態把握が可能になります。
従来のアプローチの限界
1990年代のペルソナ、1995年のライフスタイル分析(エモーショナル・プログラム)など、 消費者を類型化する アプローチが長らくマーケティングの主流でした。
- 「20代女性、都内在住、年収400万円」
- 「音楽フェス好きで週末に友人と出かける人」
- 「健康志向で環境問題に関心がある」
こうした「〜な人」といった捉え方 は、一見すると解像度が高く見えるものの、実は 消費者の実態を捉えきれていない側面があります。
なぜなら、同じ人でも:
- 時間帯によって行動が変わる
- 状況によって判断基準が変わる
- 誰と一緒かで選択が変わる
- その日の気分で欲しいものが変わる
からです。
大規模情報時代の新アプローチ
大規模情報時代には、行動を直接・間接的に把握する行動分類視点であるべきだと考えられます。

重要なのは「どんな人か」ではなく、「何をしたか」「何をしようとしているか」にあります。
- 過去の購買履歴
- サイト内の行動パターン
- 検索クエリの変遷
- コンテンツとのインタラクション
- ソーシャルメディアでの反応
こうした 行動データ から、その瞬間の消費者のニーズや意図を推測し、最適な提案を行います。
技術的進化による加速
この転換は、技術的な進化によってより進んでいくと考えられます:
- AIによるリアルタイム行動分析 :瞬時に行動パターンを認識
- 予測モデルの高度化 :次に何をするか、何を求めているかの予測精度向上
- パーソナライゼーションの深化 :一人ひとりに最適化された体験の提供
「この人はこういうタイプ」という静的な分類から、「この人は今このような状態にある」という動的な理解へとシフトしています。これが、データ起点のオーディエンスプランニングの本質と言えるでしょう。
4-2. 事業の可能性はボーダレスに
自社資産の再発見
YKKのグローバルSNS運用の事例は、極めて示唆的です。
「ゴリゴリのB2B企業」であるYKKが、なぜSNSに取り組むのか。その背景には以下の点があります:
- 発信しなければ、誰も知らない企業になってしまう (認知の問題)
- HR対策であり、社内活性化でもある (組織の問題)
- 「YKKの部品を使っているので信頼できる商品だ」という認知まで積み上げたい (ブランド価値の問題)
つまり、ファスナーという部品メーカーが、 最終製品のブランド価値にまで影響を与える存在になろうとしている点が注目されます。
常識にとらわれない模索
TinySpec(失敗したゲーム会社)がSlackへとピボットした事例が示すように、 事業の可能性は思いもよらぬところにある ことを示しています。
開発チームが内部で使っていたコミュニケーションツールが、4.2兆円の価値を持つサービスになりました。これは、 自社の資産を既存の枠組みで捉えていては見えてこない 可能性を示しています。
ボーダレス化の意味
- B2BとB2Cの境界が曖昧になる :YKKのように、部品メーカーが最終消費者に直接訴求
- 業種の枠を超える :ゲーム会社がコミュニケーションツール企業に
- 製品とメディアの融合 :製品自体が「巨大な広告塔」となる(Product is media)
- コンテンツが商品になる :「るるぶ」のように、情報コンテンツそのものが商品価値を持つ
データとAIが可能にするのは、 自社の資産や強みを、まったく新しい形で価値化すること と言えるでしょう。
「うちはメーカーだから」「うちはB2Bだから」「うちは地味な業種だから」といった固定観念にとらわれず、 事業機会は常識にとらわれない模索を続ける 姿勢が求められます。
第5章:倫理的基盤としてのDEI
DEIとは?

DEIは多様性(Diversity)、公平性(Equity)、包括性(Inclusion)を指し、組織運営・製品開発・市場コミュニケーションにおいて、信頼と持続的価値を生むための倫理的基盤です。企業にとって戦略的要素であり、単なる道徳的主張に留まりません。
5-1. 企業姿勢を表現する際の参考書としてのDEI
DEI(ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン)は、組織において:
- ダイバーシティ(多様性) :性別、年齢、国籍、障がい、価値観など、あらゆる多様な個性を尊重する
- エクイティ(公平性) :多様なニーズに合わせて支援の形を変え、誰もが公平な機会を得られるようにする
- インクルージョン(包括性) :すべての人が能力を最大限に発揮できる環境を作る
という取り組みを指します。
さらに、Belonging(帰属意識) や Accessibility(利用しやすさ)を加えて、DEIB、DEIAAと呼ばれることもあります。
5-2. なぜDEIが重要なのか
カンファレンスで示されたのは、DEIが単なる「良いこと」ではなく、 事業上の必須要件 であるという認識が示されました。
イノベーションの源泉
Jennifer Willeyが提唱した「ダブル・ダイバーシティ」の概念:
- コンポジション・ダイバーシティ(構成的・見える多様性) :性別、年齢、人種、能力など
- インフォメーショナル・ダイバーシティ(情報的・見えない多様性) :スキル、実体験、人脈(ネットワーク)など
これら2つの多様性を重ね合わせることで、イノベーションが20%向上し、問題解決能力が63%向上する という調査結果が報告されています。
つまり、DEIは以下のような価値をもたらすと考えられます:
- 企業価値の向上 :多様な視点がイノベーションを生み出し、競争力を高める
- 離職率の低下 :従業員が尊重され、能力を発揮できる環境は、働きがいを高める
- ステークホルダーからの評価向上 :消費者や投資家からの評価につながる
American Eagleの事例が示す複雑性
「Sydney Sweeney has great genes」キャンペーンは:

- 商品は完売し、株価は38%上昇、ブランド認知度も過去最高を記録
- 一方で、「白人の美の基準を強化する」として大きな反発も招いた
この事例は、 信頼がいかに複雑であるか を示していると同時に、 多様な視点の重要性 を裏付けていると言えるでしょう。
5-3. DEIは倫理的規範である
ここで重要となるのは、 DEIを「組織のあらゆる活動の倫理的基盤」として位置づける 視点です。
三者の視点
カンファレンスで語られたDEIの面白さは、 消費者、事業者、社会それぞれの視点 がある点にあります。
- 消費者の視点 :多様な人々が尊重され、自分らしくいられる製品・サービスを求める
- 事業者の視点 :組織の競争力を高め、イノベーションを生み出す経営戦略
- 社会の視点 :より公正で包摂的な社会を実現するための責任
DEIは、 事業者だけの課題ではなく、かつ事業者がはたらきかけるべき課題 と言えます。
倫理的規範としての有効性
マーケティング活動を含む 事業者活動における倫理的規範を整理するうえで、DEIは非常に有効 であると考えられます。
その理由として、DEIは以下のような特徴を持つためです:
- 抽象的な「良いこと」ではなく、 具体的な行動指針を提供する
- 短期的な利益だけでなく、 長期的な企業価値を考えさせる
- 法令遵守を超えた、 社会的責任のフレームワークを提供する

KFC中国の誤訳事例(「指までなめたくなる美味しさ」→「指を食べちまえ」)が示すのは、 文化的多様性への配慮の欠如 がブランドを毀損するということを示しています。
第6章:マーケティングの本質への回帰
「マーケティングの本質とは何か」を問うとき、AIエージェント時代において企業が果たすべきは「消費者が安心して意思決定できる環境」を設計することです。以下の4つの柱がその実践軸となります。
6-1. 発信者コントロールの終焉、再び
前述したように、 消費者自身がAIを活用して購買するようになると、受け取り側がコントロールするので、発信者側がコントロールする手法は限界を迎えると考えられます。
では、企業は何をすべきなのでしょうか。
6-2. マーケティングの本質とは?──AI時代における4つの柱
マーケティングの本来の役割は、消費者理解とR&D、情報開示とコミュニティへの貢献、に収斂していくと考えられます。
①消費者理解
「売りたいものを売る」のではなく、「求められているものを提供する」ための深い理解が求められます。
- 行動データに基づく動的な理解
- システム信頼の構造の理解
- 自信の欠如や不安の理解
②R&D(本質的に良い製品)
AIエージェントが比較検討する時代において、 表面的な差別化は通用しにくくなるでしょう。
- 本質的な品質
- 革新的な価値提供
- 持続可能性
製品自体が「巨大な広告塔」となる(Product is media)という原則が、ここでも重要になります。
③情報開示(透明性)
AIエージェントが情報を取得・評価する時代において、 透明性が競争力となると考えられます。
- 製品の詳細情報の構造化された提供
- 製造プロセスの開示
- サステナビリティ情報
- 価格の公正性
GEOの文脈でも、 信頼できる情報源として引用される ためには、透明性の高い情報開示が不可欠です。
④コミュニティへの貢献
コトラー3.0が示すように、 マーケティングは社会の共創 であるとされています。
- 帰属意識を生むコミュニティの形成(Nordstromの「The Naughty Club」、Converseの無料レコーディングスタジオ)
- 社会課題への取り組み
- より良い社会の実現への貢献
「日々をよりよく生きるために、いかに社会に役に立とうとしているか」 —これがマーケティングの重要な観点となります。
6-3. より実践的であるためには、セールスと社会的合意形成の切り分けが必要
重要なのは、 マーケティング活動が、セールスなのか、社会的合意形成なのかを、切り分け・組み立てる ことだと考えられます。
- 短期的なセールス活動 :売上を上げるための戦術的施策
- 長期的な社会的合意形成 :企業が社会において果たすべき役割の明確化と、それへの支持の獲得
両者は相反するものではなく、むしろ 後者が前者を支える構造 を作ることが、AI時代のマーケティングにおいて重要になると言えるでしょう。
第7章:総括
7-1. AI時代のマーケティング5原則とは?
Keynote #1で示された「新時代のマーケティング5つの原則」:
- 事業者がパーパスを持つ (確固たる信念)
- 帰属意識こそ最大のロイヤリティ (コミュニティの活性化)
- 消費者が誇れるブランドである (象徴的なブランド世界)
- プロダクトはメッセージである (製品はメディア)
- リアルは常に王位にある (現実世界での体験)
そしてOpening Remarks #2の「変化の時代を勝ち抜く5つの原則」:
- 事業機会は常識にとらわれない模索を続ける (カオスの中の機会)
- 顧客の信頼を勝ち取る (信頼の構築)
- 顧客外の反応に機敏である (脅威の理解)
- 冷笑的にならない (オーセンティックであること)
- 計測できないものも活用する (ダブル・ダイバーシティ)
これらは、 異なる言葉で同じ本質を語っていると言えるでしょう。
その本質とは、 企業は、消費者が安心して意思決定できる環境の設計者でなければならない ということだと考えられます。
7-2. 3者の立場、「よりよい社会へ向けて、共に、現状を変えよう」
最終的に、マーケティングとは何でしょうか。
それは、 企業・消費者・社会の三者が共に価値を創造し、より良い社会を実現していくプロセス であると言えます。
- 企業は単に製品を売るのではなく:
- 消費者が自信を持って選択できる環境を作り
- 社会的課題の解決に貢献し
- 未来への可能性を切り開く
「よりよい社会へ向けて、共に、現状を変えよう」 —これがマーケティングの本質であり、AI時代においてこそ、この原点に立ち返る必要があると考えられます。
おわりに:
AI時代の5原則
❶AIをインターフェースとして、情報基盤へ接続する
生成ではなく接続を重視する
RAG/MCPによるエコシステム構築を優先する
真の価値は「何を作るか」ではなく「何と繋がるか」
❷市場の動きを、類型分類ではなく、行動分類で観察する
ペルソナ(属性)ではなく行動データで判断する
静的な類型化ではなく動的な状態把握
「どんな人か」より「今何をしようとしているか」
❸信頼を支える市場のシステム構造に介入する
個別ブランドではなくエコシステム全体の信頼性
プラットフォーム、コミュニティ、アルゴリズムへの信頼
帰属意識→信頼→意欲→自信の好循環を設計
❹自ら市場を見つめ、応えていく
情報速度が速くなるほど、目先のニーズもよりはやく陳腐化します。
消費者自身が多様なインターフェースを持つ時代へ( Accessibility is DEAD)。
短期的なセールスと、中長期的な社会共成を意識することが求められます。
❺オーセンティックな社会共創
多様化が進む中で全員が唯一共有できる価値としてオーセンティックな社会共創。
日本での”あたりまえ”も、改めてしっかりとメッセージすることが必要と考えられます。
その際の倫理としてDEIが挙げられます。
ListeningMind がもたらす価値
生成AI、行動分類、システム信頼、DEIといった、いまマーケティングに求められる変化を整理しました。ListeningMind は、まさにこれらを支える「AI ×データ ×実行力」のプラットフォームです。
- 検索データと行動データを AI で解析し、消費者の「今・何をしようとしているか」を可視化します。
- RAG・MCP で示された「情報取得→外部接続→実行」の流れを、企業内で再現できるよう設計されています。
- システム信頼を構築するために、偏りの少ない検索基盤と透明な分析プロセスを備え、企業が「安心して選ばれるブランド」になるための仕組みを提供します。
- DEI時代の企業価値として、「多様性・公平性・包括性」をデータや施策で支え、単なる言葉ではなく、実践可能な行動に落とし込む設計を後押しします。
つまり、これからのマーケティングが求める「AIを単に使う」から「AIとどう繋がり、どう価値化するか」への移行において、ListeningMind はその橋渡しをする存在と言えます。
次のステップへ
変化の波にただ流されるのではなく、自ら設計し、先導していく。ListeningMind とともに、あなたのマーケティングを「知の対話」から「実践の行動」へと進化させませんか。