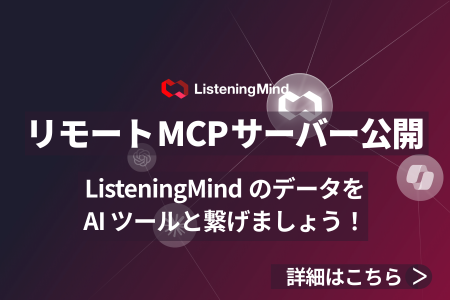健康機能食品や食品市場は、トレンドの変化が非常に速く、消費者ニーズも細分化が進んでいます。このような市場で競争優位を確保するには、消費者の「本当の意図」を正確に捉えることが重要です。
チョングンダンヘルスケアの食品マーケティングチームを率いる崔チーム長は、消費者が自発的に行う「検索」という行動に注目し、それをデータとして活用することで、従来の調査手法の限界を超え、マーケティングに必要な根拠をより効果的に得られるようになったと語ります。
今回は、リスニングマインド導入の背景や、データに基づく意思決定プロセスについて伺いました。
導入企業様の紹介
チョングンダンヘルスケアは、ラクトフィット(乳酸菌)をはじめとする多彩な製品を展開する、韓国を代表する健康機能食品メーカーです。人生の各ライフステージに寄り添い、健康維持や予防に貢献するグローバルヘルスケア企業を目指しています。

チョングンダンヘルスケアでのご担当業務について教えてください。
現在、食品マーケティングチームのチーム長を務めています。チームの主なミッションは、ブランドマーケティングを通じて売上目標を達成することです。つまり、消費者にできるだけ早くブランドを認知してもらい、実際に体験してもらうまでの一連のプロセスを担当しています。
リスニングマインドを初めて導入した2024年当時は、ブランドマネジメント(BM)チームのチーム長として、“アイムビタ”や“ラクトフィット”といった健康機能食品のブランドマーケティングを担当していました。現在はダイエットコーチやテイスティン(Tasty’n)などの一般食品ブランドも管理しています。
リスニングマインド導入の背景
リスニングマインドを導入したきっかけを教えてください。
最も大きな理由は、「消費者が自発的に参加したデータ」を分析できる点でした。
従来の消費者調査は、マーケターが設定した質問に対して消費者が回答する形式のため、どうしても消費者の視点を捉えづらいものでした。しかし検索データは、質問を投げかけなくても、消費者が自ら入力した検索語から意図(インテント)を読み取ることができます。
さらにリスニングマインドでは、データが月単位で継続的に更新されるため、消費者インテントの変化も追いやすい点が魅力です。マーケティングの観点で見ると、月次更新というサイクルは、ほぼリアルタイムでのインサイト把握が可能だと感じています。
リスニングマインドの活用方法
印象に残っている活用プロジェクトについて教えてください。
リスニングマインドは、重要な意思決定が求められるプロジェクトで主に活用しています。代表的な例として、「ラクトフィット再活性化プロジェクト」と「アイムビタのビッグ・コミュニケーション戦略」があります。
■ ラクトフィット:再活性化戦略のためのカテゴリー調査
ブランド再活性化に向け、「どこで停滞が起きているのか」「実際のユーザーは誰なのか」「どの年齢層が検索しているのか」といった問いに対し、オーガニックデータを分析しました。特に、検索経路と経路上に出現するキーワードを活用することで、リアルな消費者行動の把握が可能になりました。
その結果、「ライフステージ別の乳酸菌」という既存のブランドスローガンを、「ライフステージからニーズケアまで対応する乳酸菌」へとアップデートすることができました。
■ アイムビタ:コアバリューに基づくコミュニケーション戦略立案
後発ブランドとして市場に参入したアイムビタでは、的確なポジショニングが求められました。ブランドのコアバリューが「いかに早くエネルギーを高められるか」であると再定義し、「1ショット・1デイ」というスローガンのもと、即効性を訴求するコミュニケーション戦略を展開しました。
これらのプロジェクトで特に役立ったのが、パスファインダーとクラスターファインダーです。
従来の分析ツールでは追跡できなかった検索経路も、パスファインダーで可視化され、探索過程や最終の着地点も把握できます。これにより、検索過程の中で使われるキーワードを先回りして把握し、マーケティング戦略に活かすことが可能になりました。
また、インテントファインダーも非常に有効でした。複数ワードを組み合わせるよりも、代表的なキーワードを深掘りする方がインサイトを捉えやすいと感じています。たとえば「ダイエット運動」といった具体語より、「ダイエット」という大分類の方が、本質に近づきやすい印象です。
加えて、年齢層や検索量でのフィルター機能も大きな助けになりました。
導入後の変化と効果
リスニングマインド導入前後での違いや効果について教えてください。
以前は、主に消費者調査を通じてデータを収集していました。しかしこの方法は時間もコストもかかるため、年に1~2回しか実施できず、タイムリーな意思決定が困難でした。調査の準備に3か月、実施から結果取得までにさらに3か月と、半年がかりになるケースも珍しくなく、トレンドへの迅速な対応は難しかったです。特に新しいカテゴリーに参入する際は、さらに多くのリソースを要しました。
一方、リスニングマインドはサブスクリプション形式で、コスト効率が高く、意思決定に必要なヒントや根拠を提供してくれます。
私が以前勤務していた飲料メーカーでは、試飲調査では約80%が「おいしい」と回答したにもかかわらず、実際の市場では商品が売れないということが頻繁にありました。オンライン上のデータも活用してみましたが、マーケティング目的で作られた情報が多く、消費者の“本音”を掴むのは難しかったです。
その点、リスニングマインドは消費者の検索データをもとにしており、「実際の意図」に迫ることができます。
リスニングマインドの導入によって社内の意思決定にどのような変化がありましたか?
中長期的なブランドポートフォリオを構築する上で、リスニングマインドは重要な意思決定ツールになっています。
たとえば、疾患領域の成長性を判断する際、健康保険のデータなど定量情報だけでは、消費者の関心度までは見えません。しかしリスニングマインドを使えば、「関節市場はどうか」「コンドロイチンはどの年齢層が注目しているのか」「検索起点はどこにあるのか」など、具体的な関心の動きを把握できます。
社内のマーケティング会議でもリスニングマインドのデータを活用し、「消費者はこう考えている」「この層がこのキーワードを多く検索している」といったインサイトを提示することで、客観的な意思決定を支えられるようになりました。
今後の展望
最後に、今後の展望やリスニングマインドに期待することを教えてください。
食品市場は「一般食品市場」「健康志向食品市場」「健康機能食品市場」の3つに分かれます。高齢化社会の進行により、今後は多くの食品が自然と“健康志向”にシフトしていくと考えられます。その中で、健康志向食品市場は今後も大きく成長していくでしょう。
私たちも、それに応じてより多くの商品を開発していく必要があります。これまで複数のブランドをデータドリブンで成長させてきたように、今後は食品領域でも、リスニングマインドの顧客インテントデータを基盤にブランドを育てていきたいと考えています。
リスニングマインドの活用領域も、今後ますます広がっていくはずです。
もし、「消費者ベースのデータをどう集めるか」で悩んでいる企業がいらっしゃるなら、リスニングマインドは非常に有効なソリューションとなるでしょう。そのためにも、マーケター同士が活用法を共有できるコミュニティや、ノウハウを交換し合える場があると良いですね。
本日は貴重なお話をありがとうございました。
この記事のタグ